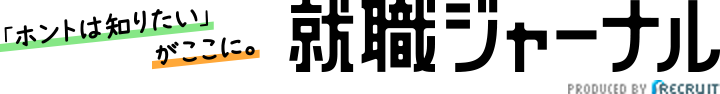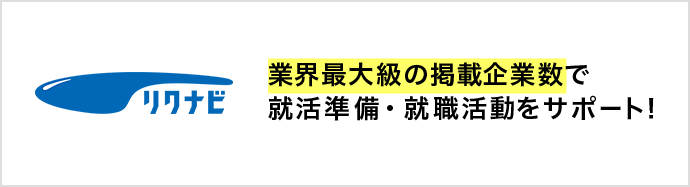すおまさゆき・1956年東京都生まれ。81年立教大学文学部仏文科卒業。在学中から映画の現場に入り、84年成人映画『変態家族 兄貴の嫁さん』で監督デビュー。89年『ファンシイダンス』で一般映画を初めて監督する。92年『シコふんじゃった。』で日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞。96年『Shall we ダンス?』で日本アカデミー賞13部門独占受賞。以降の作品に『それでもボクはやってない』(2007年)、『ダンシング・チャップリン』(11年)、『終の信託』(12年)、『舞妓はレディ』(14年)。11年から13年までは法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」の委員も務めた。
「所詮、映画でしょ」とは言わせないものを作りたい
僕は映画のネタ探しはしません。ネタを探すと映画を作りやすいように現実を見てしまいそうで。そうならないよう、まずは僕自身が関心を持ったこと、知りたいことを取材し、うまくいけば映画になるという感じでやってきました。ここ10年ほど関心を持ち続けているテーマに「刑事司法」がありますが、そのきっかけは、痴漢事件で逆転無罪判決が出たことを報じた新聞記事。被告人の友人たちが弁護団に協力して裁判を闘ったと知り、単純に感動的な話だなと思ったんです。ところが事件の当事者にお話をうかがったり、痴漢えん罪を訴える人たちの会に参加してみると、日本の刑事裁判というものが僕のイメージしていたものとは大きく異なることがわかり、ショックを受けました。
例えば痴漢行為を疑われた人が勾留(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者で、住所不定ないし証拠の隠滅または逃亡のおそれがある者を一定期間拘束すること)されると、否認を続ける限り、多くの場合、裁判で被害者証言が終わるまで釈放されることはありませんでした(注:最近の痴漢事件では、否認すれば必ず長期間勾留されるというわけではないと言われている)。裁判で無罪を立証したくても、自ら動いて証拠を集めることができず、裁判の知識がないために適切な弁護士を依頼することもできず、最終的には被害者証言のみで有罪判決が下るというケースが多かった。一方、逮捕後すぐに罪を認めると、前科がついて数万〜数十万円の罰金を払うことになりますが、うまくいけば会社にも家族にも知られずにすみます。勝つ見込みのほとんどない裁判を長期間闘うよりも早く解放されたいと、被告人が虚偽の自白をすることもあります。そんなおかしなことがあるのかと思いますよね。でも、実際にあるんです。
刑事司法について調べれば調べるほど疑問が生まれ、「これは映画にしなければ」と撮ったのが『それでもボクはやってない』です。取材には3年半かかりました。刑事裁判を200回以上傍聴し、何人もの弁護士のお話を聞き、数百冊の専門書を読みました。その末に嫌というほど思い知らされたのは、日本の司法実務では必ずしも人権が守られているわけではないという現実です。映画公開後も問題意識は消えず、2011年から14年まで法制審議会の特別部会「新時代の刑事司法制度特別部会」の委員を務めました。近年検察の証拠改ざんが明るみに出たり、「足利事件」のえん罪を認める判決が出るなど刑事司法の世界の不祥事が社会問題になる中、制度改革の必要性が指摘されて設置された部会でした。
この部会で僕が主張したのはおもに、否認していると勾留される「人質司法」と呼ばれる勾留の適正化、検察官に証拠隠しをさせないための証拠の事前全面一括開示、不正に調書が作られないようにする取り調べの録音・録画。刑事司法の取材を重ねる中で大きな疑問を感じており、最低でもこれだけは何とかしなければと、同じ意見を持つ委員の皆さんと一緒にできる限りのことをしたつもりです。しかし、従来の取り調べ方法に肯定的な方々との議論はかみ合わず、この部会の議論を基に作られた関連改正法案に大きな改革は見られませんでした。不本意ですが、嘆いていても何も変わりません。多くの人に日本の刑事司法の世界で起きている現実を知ってほしいと、この会議での体験を『それでもボクは会議で闘う』という本に書きました。
新聞などのマスコミでは「拘留(刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設で身柄を拘束すること)」と区別するためなのか何なのか「勾留」を「拘置」としたり、「被害者」と音が似ていることから「被疑者」を「容疑者」とするなど法律用語にはない言葉を使うことがあります。でも、この本では耳になじみのない法律用語もあえてそのまま使いました。一般の人にはわかりにくい言葉で行われているのが刑事司法の現場で、もし、僕たちが罪もないのに疑われて裁判を受けることになったら、そんな言葉が飛び交う場で闘わなければいけない。その現実を伝えたかったからです。
映画『それでもボクはやってない』を撮る時も、「日本の裁判とはこういうものですよ」ということを僕が見たままに、間違いなく、正確に伝えたいと思っていました。そのための取材を通して、これまでの映画やドラマで描かれている裁判と現実があまりに違うことに驚きました。例えば、よく裁判官が小槌をたたいて「静粛に」というシーンがありますが、日本の裁判官は小槌を使いません。
映画やドラマを作るときは法律の専門家が監修しているはずなのに、そんなことが起きるなんてひどいなと感じました。その話をある弁護士さんにしたら、「だって、所詮、映画でしょ」と言われたんです。彼に悪気はありません。ただ、その「所詮映画」に僕は子どものころから心を揺さぶられてきました。僕にとっては大事なものですから、「どうせ作り物なんだから、多少はうそがあってもいい」という姿勢にはなれません。もちろん、誰もが「うそ」だとわかるものを、見る人を楽しませるために描くやり方もある。でも、刑事司法という社会的影響の大きなテーマでうそを伝えるわけにはいかない。作り手と観客との間には約束事というのがあって、それを裏切ってはいけないという責任が僕にはある。だから、「所詮映画」とは言わせないものを作ろうという思いは常に抱いています。

世界はあなたが考えるよりずっと広い。それを覚えておいてほしい
映画をのめりこむように見始めたのは高校時代。テレビドラマも小学生の頃からよく観ていて、特に山田太一さん脚本の作品が大好きでした。子どものころから打ち込んでいた野球で挫折し、一体これから何をやったらいいんだろうと思っていた当時の僕にとって、映画やドラマは人生のよりどころとも言っていいもの。それだけに映画を難しく考え、自分が映画を撮ることなど考えたこともありませんでした。
映画を撮りたいと思うようになったのは、大学の一般教養課程で映画評論家の蓮實(はすみ)重彦さんの講義を受けた時に「映画は読むものではなく観るもので、映っているものがすべて」というお話を聞き、自分にも撮れるかもしれないと思ったのがきっかけです。「映っているものがすべてなら、僕自身が興味を持ったものを素直に撮れば、映画になる。それならできそうだ」と都合よく解釈したんです。
就職活動の時期になり、どうやったら映画の世界に行けるだろうと調べましたが、助監督を募集していたのは日活だけで、過去に採用された人たちを見ると、東京大学をはじめとする国立大や一流私大の卒業生ばかり。僕には無理だと思いました。そんな時に、当時スタッフとしてお手伝いしていた小劇団の女優さんから、映画監督の高橋伴明さんが彼女のアルバイト先によく来ると聞いて。新宿・ゴールデン街のバーで伴明さんに頼み込んで、成人映画の制作現場に出入りするようになりました。
最初の1カ月半は電話番で、助監督としての初仕事は、監督の「カット!」の声を聞いたら、裸の女優さんにタオルをかけること。3年ほどでチーフ助監督になりましたが、ひとつの作品を撮るために2カ月昼夜問わず働いて、ギャランティは7万円。当時喫茶店のウエイターのアルバイトが時給400円ほどでしたから、喫茶店のアルバイトの方が圧倒的に高給でした。それでも、本気でモノ作りをしている人たちに囲まれて仕事をするのが楽しかった。ただ、成人映画というのは撮影場所ひとつ探すにもひと苦労で、やむを得ず「学生の自主映画です」などと撮影場所の管理者にうそをついて撮影をすることもありました。作り手側はジャンルが何であれ、気概を持って作品を作っているのに、世間にうそをつかなければいけない。それが苦しくて。映画の現場に入って5年目に「そろそろ1本、監督をやってみる?」と言われたのですが、実はその時には「この1本を好き放題やって、もし監督の仕事に魅力を感じなかったらやめよう」と考えていました。
ところが、いざ作品を撮ろうとすると、「好き放題」どころか何を撮っていいのかわからない。映画への憧れだけでこの世界に入り、自分が何を撮りたいのかを突き詰めてこなかったことに気づいて途方に暮れました。しばらく「どうしたらいいのかな」と考えて、立ち返ったのが「自分の興味を持った世界を撮る」という映画監督を志した原点。自分の一番好きなものを撮ろうと決め、完成したのが『変態家族 兄貴の嫁さん』。敬愛する小津安二郎さんの監督作品を研究し、その撮影作法を徹底的に模倣した作品です。
5日間ほとんど寝ずに撮影しましたが、監督として自分の意思ですべてを決定して作品を撮るのは楽しかったです。世界がバラ色に見えるほど(笑)。おまけに恩師の蓮實さんが批評でほめてくれ、若い映画ファンや映画関係者が劇場に足を運んでくれました。その後しばらくして伊丹十三監督作『マルサの女』のメイキング番組の話が来て成人映画から離れ、32歳の時に『ファンシイダンス』で初めて一般映画の監督をしました。
以後、廃部寸前の弱小相撲部に入ることになった大学生の奮闘ぶりを描いた『シコふんじゃった。』から2014年に公開された舞妓を目指す少女の成長物語『舞妓はレディ』に至るまで、僕の作る映画は「物事はやってみないとわからない」という話ばかり。それは僕自身の経験したことそのものです。大学に入ったころは映画監督になれるなんて思ってもいなかったし、成人映画の現場にいた時は、自分が今のような作品を撮るなんて想像もしていなかった。でも、いろいろな人と出会い、いろいろな仕事を経験していくうちに、自分が何に興味を持っているのか、それをどう深め、アウトプットしていくのかを少しずつ学んでいったんです。
僕たちの時代ですら「情報化社会」と言われていたのに、今は当時の比ではないほど情報があふれていて、何もやらなくても世界を知った気になってしまいがちです。でも、よく若い人たちに言うのは「世界はあなたが考えているよりずっと広い」ということです。世界は学生時代までに得た知識や情報では計り知れないほど広い。本当にいろいろな人がいて、仕事を含めいろいろな場があるから、そのことを覚えておいてほしい。初めから「こんなもの」と決めつけず、何にでも向き合ってみることが大事なのではと思います。
幸運なことに僕は自分のやりたいことをやり、それを今のところは何とか収入に結び付けられています。収入になるというのは、自分のやったことが人に必要とされているということですよね。映画を撮るにしても、本を書くにしても、見たり、読んでくれた人の反応がなかったら、きっとできない。スルーされていたら、次を作る意欲はなくなると思うんです。見てくれる人がいる、読んでくれる人がひとりでもいるという実感。もう本当に、それが最高の喜びなんですよ。自分が誰かの役に立っているとか、感謝をされているとか、必要とされているという実感というのは、生きるモチベーションになる。仕事というのはその実感を得られる一つのツールだと思います。

INFORMATION
周防さんが法制審議会の委員会で活動した3年間をつづった『それでもボクは会議で闘う—ドキュメント刑事司法改革』(岩波書店/税抜き1700円)。警察や検察の取り調べを改革するための法案づくりが会議の最終目的で、テーマは多岐に及んだが、本書では「取り調べの録音・録画」「証拠の事前全面一括開示」「人質司法と呼ばれる勾留の適正化」の3点について改革を進めようとする周防さんと、現状に肯定的な警察・検察関係者との議論の一部始終がつまびらかにされている。

取材・文/泉彩子 撮影/鈴木慶子