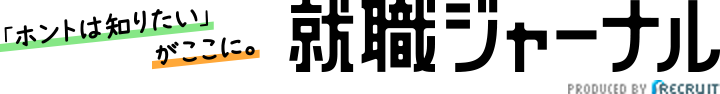1社にターゲットを絞り、自らの足で情報を稼いだ就職活動
私が新卒の就職活動で受けた会社は、読売新聞1社のみ。もし不合格だったら1年留年して翌年またチャレンジしよう。そう退路を断って活動に臨みました。
学生時代はそれほど授業にも出なかったし、何かにすごく力を注いだ、ということもなかった。どちらかといえば凡俗な学生だったと思います。ただ、中学校、高校のころから文章を読んだり書いたりすることが好きで、「筆で身を立てる」というほどの過信はありませんでしたが、そうしたことが職業として向いているのではないか、と感じていました。 文を書く、という職業の中にも、多様な選択肢があります。新聞記者という道を選んだのは、知人や友人を通じて新聞記者の大先輩の話を聞いたり、本を読んだりする中で、社会正義をペンの力で実践するということに、魅力を感じたからでした。
今でこそ、読売新聞は発行部数世界一の新聞ですが、当時は朝日新聞に比べて後れを取っていました。しかし、私にとっては子どものころから読み慣れた新聞であり、また、私の故郷、富山は読売中興の祖である正力松太郎の出身地。さらに、出身高校も彼と同じ。そんな身近さがあったうえに、他紙と比べると、紙面の持ち味や伝統、論説の色合いなどが、自分に最も合うのではないか、とも思いました。どこか野武士的で、 “伸びしろ”が大きい。そんな勢いに引きつけられて、「1社しか受けない」という大胆な行動に出たのだと思います。
ターゲットを読売新聞に絞ってから、入社試験に向けて、私なりに入念な準備を重ねました。当時の試験は一般常識とエッセイ、そして面接。半年ほど前から過去の新聞記事を読み返し、エッセイの過去問題を検討して新しい課題を自分で作って書く。そして、京都支局(現在の京都総局)をアポなしで訪問し、「入社試験を受けるので添削してください」と幾度かお願いしました。また、上京した際には警視庁記者クラブにある読売新聞のボックス(部屋)に、やはりアポなしで行ったこともありました。そんな無鉄砲な私を受け入れ、添削したり、話を聞かせてくれたりする記者の存在が、より入社への意欲をかき立てました。
こうした準備が功を奏して、無事合格できたのです。
1つにターゲットを絞ったからこそ、集中した取り組みができました。今振り返っても特によかったと思うのは、入社前、足で稼いでいろんな人に会って話を聞いたこと。時代背景が異なるところはあるものの、皆さんにもやはり、「ここ」という企業にターゲットを絞ったら、Web上の情報に頼るだけでなく、先輩訪問などでリアルな情報を得る努力をしてほしい。私自身、リアルな情報を得ていたので、入社後あまりギャップを感じることはなく、仕事に自然になじんでいけたのだと思います。

やりたいことが原点にあれば、壁を乗り越えられる
入社後は、地方支局を経験します。まず、1年目は「警察回り」からスタート。交通事故などの取材をして、それを記事にするなどしました。その後、本人の適性や希望、地方支局での評価によって、政治部、経済部、国際部、社会部などへの配属が決まります。この仕組みは、今も当時もあまり変わっていません。私の場合、最初の配属は静岡支局。その後、福島、郡山と回りました。先ほど、「入社後ギャップがなかった」とお話ししましたが、その大きな理由は生活スタイルにあったと思います。学生時代は試験に通れば、自分の責任で少しくらい授業に出なくても許される面もある。新聞記者の仕事も、締め切りに原稿が間に合えば、多少の息抜きもできるし、自分の時間も持てます。
ペンの力で社会に影響を与えたい。天下国家を論じてみたい。新聞記者志望者は、少なからずそうした大望を抱いて入社します。私もその例にもれず、でしたが、書く記事と言えば、「何時何分にどこで交通事故があり、何人のケガ人が出た」というようなものばかりでしたから、仕事に不満はありました。
そんな時代を乗り切ることができたのは、自社、他社を問わず、多くの大先輩の存在があったからでした。尊敬できる先輩たちも、同じ道をくぐってきた。大きな仕事を成すには、小さな仕事の積み重ねがあってこそ。すべてを受け入れられたわけではありませんでしたが、そうやって自分を納得させていました。
また、自分が手を抜くと、自分に跳ね返ってくることもだんだんわかってきます。しょっちゅうあってはならないことですが、他紙に「抜かれる(スクープ記事を書かれる)」という失敗もありました。その一方で、人に会って、コツコツと情報を集めるという地味な仕事の積み重ねが、成果につながる、という経験もしました。
「旧聞話者になるな」。先輩に諭された言葉が、今も胸に残っています。新聞記者とは、新しく聞いたことを正しく書く職業である。旧聞に属する情報を自分が得た情報のように書いてはならない。そして、いくら新しい情報であっても、確認せずに記事にして、誤報となってはならない、と。このようにして、学生時代の甘えを徐々に切り離していきました。
私にとって「仕事とは?」と問われたら、まず、「食いぶち」だと答えます。半分冗談ですが、食べていかなければならないのも事実です。しかし、私が幸せだと思うのは、「食いぶち」であることを意識せずに仕事を続けてこられたこと。すべての人にとってではないと思いますが、私の選んだ仕事は食いぶちであり、同時に趣味であり、生活であり、道楽でもありました。
私は、地方支局を経験した後、政治部を希望し、そして配属されました。入社したころはワシントンやパリなど、世界を股にかけて仕事をしたいと思っていましたが、特派員という立場ではその国のトップや政治家を直に取材するのがなかなか難しいことだとわかってきました。政治部であれば、日本のトップから一次情報を得ることもできる。そう気持ちが変わって、政治部記者を志すようになったのです。
当時政権を執っていた自由民主党の総裁選。キャップとして何人かのチームを率いて、抜くか抜かれるか、というような厳しい勝ち負けの世界を経験しました。誰かが1対1ですごい情報を教えてくれて、世紀のスクープ、というようなことはめったにありません。とっかかりを見つけたら、そこを必死に深掘りして、ダイヤモンドや金を探り当てることもあれば、そうでないこともある。日々、緊張の連続でした。仕事は、山もあれば谷もある。それでも、いい原稿が書けた、誰かが喜んでくれたという経験をし、自分の書いたものが、ある意味で人を、社会を動かすという力を実感できる、大きな喜びをもたらしてくれる、仕事とはそういう存在なのです。
なぜそのような存在になり得たのか。
その理由は、就職活動に原点があります。今、経営者というポジションにいますが、それを望んで入社したわけではありません。新聞記者という職業で身を立てたい、という一心で、この会社の門をたたきました。日本の社会・経済環境が厳しくなればなるほど将来勝ち残る企業を選びたい、という学生の皆さんの気持ちも理解できますが、社会に出てから次々と目の前にやってくる壁を乗り越えるには、そして、満足した仕事人生を送るには、自分がやりたいこと、求めるものに近い企業活動をしている会社を選ぶべきです。そして、もしそういう会社がないのであれば、自ら起業することを視野に入れる、つまり、職に就くのではなく、職を作る気概も必要ではないでしょうか。
新人時代
プライベート
取材・文/入倉由理子 撮影/刑部友康 デザイン/ラナデザインアソシエイツ
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。