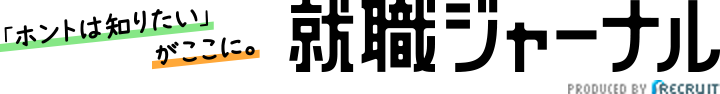生意気な新人時代。自分なりの工夫の積み重ねで成果を出す
新卒の就職活動時、私はターゲットを味の素一本に絞っていました。
父が食品関係の会社にいたこともあり、小さなときから食に関心がありました。誕生日や成績が上がったときなどは小さなイベントがあって、外食や家でのちょっとしたご馳走など、それはいつも「食」にまつわるものだったのです。
ですから、食品業界を選んだことは、私にとってとても自然なことだったように思います。
では、食品業界のなかでもなぜ、味の素を選んだのか。1つは当時から海外進出に積極的で、国内でもジョイントベンチャーを多く立ち上げるなど、国内外を問わず事業拡大しようという姿勢が魅力的でした。そうした会社の成長に合わせて、自分が働いて役に立てるフィールドが何かあるのではないかと思ったのです。
学生時代にも、ミュージカルのサークルとコントラクトブリッジ(カードゲームの一種)の会を自ら立ち上げるなど、新しいことに挑戦したり、人を巻き込みながら実行することが好きだったのだと思います。
さらに、味の素という会社に、「科学」の香りを感じていました。当社は技術者や研究所を多く抱え、食品の領域はもちろん、医療やバイオといった領域にも積極的に展開する「技術立社」です。とはいえ、これは入社後によくわかったことでしたが(笑)。当時は単に、おいしいものを提供する、というだけではなくて、うま味成分であるグルタミン酸を基にした事業展開に、科学技術の面白さを感じていたのでしょう。
入社時は大阪で、卸問屋さん向けの営業に携わりました。担当は、「クノール」というスープのブランド。最初の1、2年は無我夢中で過ごし、優秀な先輩たちに囲まれて、徐々に仕事を覚えていきました。流通再編の波が押し寄せていた当時、大事なお客さまである問屋さんの社長に向かって、「既存のビジネスのやり方では生き残っていけませんよ」などと生意気なことを言い、「出入り禁止」になりかけて、課長に救われたこともありましたね(笑)。頭でっかちになっていたところもあるとはいえ、仕事に対する問題意識やこだわりがあったのでしょう。
それは、日々の業務のなかにも表れていきました。私の担当には、キャッシュ&キャリーと呼ばれる現金問屋さんが多かったのですが、ここでは一般の問屋さんと違って、商品の配送をせずに、買い手である小売店さんが問屋さんまで足を運んで商品を購入します。現金商売だからこそ、在庫に関してはとても厳しい。そこで問屋さんに不良在庫や返品が出ないように、小売店さんに買ってほしい商品を中心に、見やすいところに並べるような、今思えばインストアマーチャンダイジングのはしりのようなことを必死で考えて工夫していました。
これが本社の目に留まり、4年目に、マーケティング部門に異動するきっかけとなったようです。

合弁事業で培われた「地域性の重視」がグローバル事業の礎に
「キャリアのバックグラウンドは何ですか?」と尋ねられたら、私はマーケティングと答えます。異動後、セールスプロモーションに始まって、広告、販売企画、製品開発、事業管理と役割を変えながら、マーケティングという仕事に約11年間携わりました。これは当社では異例の長さですが、仕事の領域がどんどん広がっていったので、飽きることは一度もなく、とても楽しく過ごすことができました。
ここでも、担当はクノールブランドのスープ事業でした。クノールスープはアメリカとの合弁事業であり、アメリカから派遣された合弁先の担当者との仕事が多くあります。彼らの合理的なものの考え方に驚かされたのと同時に、また、勉強にもなりました。
例えば、書類の書き方一つを取っても、日本のそれとは違う。日本で慣れ親しんだ書き方で、ある意味「だらだらした」書類を提出すると、すぐに突き返されます。何を、どういう目的でやるのか。実行した後、どう追跡・評価して次につなげるか。これらを簡潔に書くことが求められたのです。
これが癖になって、当時、妻の話に対して「目的は何?」などと聞き返すと、すごくいやがられましたね(笑)。
また、日本のマーケットをどう見るか、という点で、常に合弁先とぶつかっていました。彼らは地域性をなかなか納得してくれません。嗜好品は地域性を入れると良くない、と一般的に言われますが、一方でスープのような加工食品は、その土地その土地の食習慣、味覚を反映しないと、なかなか売れないのです。
例えば「クノールカップスープ」。テレビコマーシャルを見れば一目瞭然ですが、日本では朝に飲む、という習慣があります。しかし、これは世界でも稀な習慣で、欧米では昼食や夕食に飲むものです。さらに、人気の商品も違う。日本ではコーンスープが主流ですが、アメリカではトマトスープやチキンヌードルスープが売れ筋です。こうした食習慣や味覚の違いを理解したうえで販売しないと、思うような結果を得られません。
合弁先に納得してもらうプロセスのなかで、こうしたセオリーが体にすり込まれていきました。
これらの経験は、グローバル展開を進める今、とても役に立っています。
食品業界には、「グローバルジャイアンツ」と呼ばれる世界企業がいくつかあります。世界の市場では、当社は彼らと戦っていかなければなりません。世界での規模においては彼らのほうが圧倒的に大きいものの、国々のビジネスにおいては、決して負けていない。その理由は、私たちが世界各国に展開するとき、地域性を重視しているからだと思います。
商品を作るための技術は、日本から持っていきます。しかし、それを現地の食習慣や味覚に合わせるのは現地の社員の仕事だと考えています。日本人のマネジャーは現地の社員の考え方を理解するために、現地の言葉を学び、現地の人たちと同じ食事をします。グローバルジャイアンツの多くは現場にあまり出向かないが、私たちは現場で仕事をする。それが、味の素の優位性の源になっている。そう信じて、より多くの国にビジネスを広げていこうとしています。
「味の素」や「ほんだし」など、昔からのロングセラー商品が当社にはあります。とはいえ、世界を見ると栄養過剰の国もあれば、栄養不良の国もある。国内を見ても、食品の安全性が厳しく問われる時代であり、業界を取り巻く環境は大きく変わっています。「おいしく食べる」だけではなく、「生命を維持する」「健康を守る」という役割や期待を食品業界は担っており、私たち味の素の仕事がますます重要になっていることは間違いありません。
物事の本質を追究する精神で、うま味を発見した池田菊苗博士や、開拓者精神を持って事業拡大にまい進した鈴木三郎助(味の素の創業者)がそうであったように、「もっと良いものを創り出したい」「もっとこうしたら売れるはずだ」、私はそんな気持ちで常に仕事に取り組んできました。私たち味の素が、先程述べた、世のなかから期待される役割を果たしていくためには、リスクを取ってでも新しい価値を追求し、常に挑戦していかなければなりません。会議で全員が同意するようなアイディアは、見方を変えれば、そこに新しさはないのかもしれません。自分が出したアイディアを全員が反対しても、それを貫き具現化する情熱が大切ですし、また、私をはじめリーダーたちは、その風土を尊重し続ける。こうした姿勢が、新しい価値を創っていくのではないでしょうか。
新人時代

プライベート
取材・文/入倉由理子 撮影/刑部友康 デザイン/ラナデザインアソシエイツ
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。