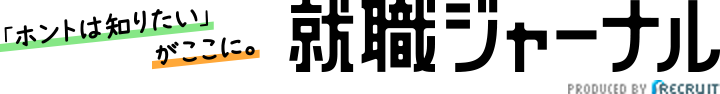ささもと・つねこ●1914年、東京都生まれ。1940年、財団法人写真協会に入職。著名人や文化人、海外使節団の動向などを取材。雑誌『婦人公論』で「日本最初の報道写真家」として紹介された。戦後はフリーの報道写真家として活躍し、三井三池争議、60年安保などを追った社会派の写真も多い。一時期写真から遠ざかるも、1985年、71歳の時に写真展を開催し、活動を再開。以後、明治生まれの女性たちを題材に撮り続け、宇野千代、壷井栄、杉村春子らを撮影した「明治生まれの女性たち」シリーズは代表作となった。2016年、アメリカのルーシー賞ライフタイム・アチーブメント部門賞を受賞。同年、公益社団法人日本写真家協会が「笹本恒子写真賞」を創設。100歳を超えた現在も現役のフォトジャーナリストとして活動している。
働く女性の少なかった時代、自分の腕で生きていきたかった
-もともとは画家志望だったそうですね。
画家に憧れて10代後半から先生について油絵を習い、卒業後は女子美術専門学校(現・女子美術大学)に行きたいと思っていました。満州事変(1931年)が起きたころのことで、女性は「お嫁さん」になるのが当たり前の時代。もちろん、両親は大反対です。「女の絵描きなんてとんでもない。絵描きで食べていけるわけがない」と叱られました。それでも頑として譲らないわたくしに、担任の先生が「家政科の特待生を募集している学校があるから、絵の勉強をしながらここに通って先生の資格を取っては?」と勧めてくださり、大妻技芸学校の高等家政科(現・大妻女子大学)に入学しました。
ところが、わたくしは少しでも早く画家になりたくて、すぐに学校を辞めてしまいました。その後は絵画研究所の夜間部に通い、学費のために昼間は事務の仕事。そのかたわらで洋裁学校にも行きました。絵で食べていけなくても、技術があれば生きていけるだろうと考えたからです。実際、その通りだったと思います。後にわたくしは画家ではなく写真家になりましたけど、写真の仕事がなくなった時期に、洋裁の技術のおかげで救われました。自分の腕で生きていきたいという思いは学生時代からありましたね。
「日本で初めての女性報道写真家になりませんか?」の言葉に心が躍った
-写真との出合いは?
とにかく絵描きになりたい一心でいろいろとやっているうちに、子どものころにお隣に住んでいらした東京日日新聞(現・毎日新聞)の社会部長・小坂新夫さんから「コラムのカットを描いてみては?」と勧めていただいて。張り切って30枚お持ちしたところ採用され、ちょこちょこと依頼してもらえるようになりました。小さなカットでしたが、自分の描いたものが新聞に載るなんてと本当にうれしかったものです。ところが、ある日、いつものコラムに私のものではないカットが掲載されていましてね。友人に「私ではなく、棟方志功(むなかた・しこう)という人の絵だったのよ」と話すと、「そうかあ」と同情してくれつつ、「棟方さんというのは、売れっ子の版画家だよ」と聞かされて(笑)。
カットの仕事がなくなってがっかりしていた時に、小坂さんが「うちの社会部にいた林謙一というのが、海外に写真を配信する『財団法人写真協会』というのを作ったんだよ。ちょっと寄ってみてはどうかな」と言ってくださったんです。「なんだか面白そう」とすぐに事務所にうかがったところ、新聞や雑誌が山のように積まれた中に、林さんがいらっしゃいましてね。報道写真への思いを語ってくださいました。当時は日中戦争下。林さんには戦地での特派員経験があり、「戦時下では宣伝戦も大事。日本について世界に正しく伝えなければ」と協会を設立したとのお話で、言葉に熱がこもっていました。
そのときに、「報道写真家」なる人たちが撮影した写真を初めて見せてもらったんです。ヒトラーが側近と歩いていたり、ムッソリーニが街の人々と談笑したりしている様子などが写されていました。新聞では見たことのない彼らの表情が印象的で、報道の力を感じました。それらの写真を手に取りながら、林さんが「日本には報道写真家はまだ少ない。女性は1人もいません。でも、アメリカには女性の報道写真家が何人かいましてね。先日はマーガレット・バーク=ホワイトさんという人の写真が雑誌『ライフ』の表紙になったんですよ」と教えてくれたんです。『ライフ』を読んだことはありませんでしたが、兄が購読していて、表紙の写真の迫力は心に残っていました。あの写真を女性が撮ったなんてと衝撃を受けました。おまけに、いきなり林さんが「どうですか。日本で初めての女性報道写真家になってみませんか?」とおっしゃって、驚きのあまり言葉がありませんでした。
-それまで写真を撮ったことはあったのですか?
カメラを持ったことはほとんどありませんでした。技術もなく、引っ込み思案な自分に務まるのか自信がなく、一度は電話でお断りしたんです。でも、「日本で初めての女性報道写真家に」という林さんの言葉が忘れられず、数時間後に事務所を訪ねて「やらせてください」と言いました。前例のないことだからこそ「やってみたい」と心が躍り、やらなければ後悔すると思ったんです。
「ここは学校でも教習所でもない」。上司の厳しい言葉に成長を促された
―ところが、写真協会にお入りになって数カ月でお母さまが病に倒れ、看病のために1年近く休職されたそうですね。
職場に戻ったら林さんは異動されていて、心細く感じました。新たな上司となる稲葉熊野さんにごあいさつをしたところ、「どうしてもカメラをやりたいんですか」と聞かれましてね。「はい」と答えたら、「わかりました。ここは学校でも教習所でもありませんから、明日からみんなと同じように仕事をしてもらいます。よろしいですか」と強い口調で言われました。本来なら、そこで辞退するものなのかもしれません。でも、勇気を出して「やらせていただきます」と声を振り絞りました。時は日中戦争の真っただ中。休職中の私は、世の中が騒がしくなっていく様子を見ながら、「自分も何か社会に役立ちたい」と居ても立ってもいられない思いでした。その思いをかなえられる場にようやく戻ったのだから、引き下がるわけにはいかなかったのです。
―写真協会では、国内外のVIPや外国使節団の撮影も多かったとか。
撮り直しが利きませんし、今のようにデジタルカメラで写したものをその場で確認できる時代ではありませんでしたから、怖くて。ただ、わたくしは仕事となると、普段はとてもできないような思い切ったことをしてしまうところがあるんです。復職して2カ月目に初めて組写真(※)を任された時のこと。上野動物園で「尾長鶏と東天紅のコンクール」の取材があり、尾長鶏の全身を撮影する必要があったのですが、どう頑張っても構図に収まりません。やむを得ず、乾いた土の上に寝そべって撮影を終えたところ、周囲から笑い声が。その日のわたくしはスーツに黒のベルベットのコート、ハイヒールという服装で、ハッと自分の姿を見ると、まるできな粉餅。自分でも笑ってしまいました。ほかにも、海外の使節団の偉い人につたない英語で「もう一度撮らせてください」とお願いしたり。思い返すと冷や汗ものですが、当時は無我夢中でした。
※あるテーマを複数の写真で表現する手法。撮影技術だけでなく、全体の構成力が求められる。
写真の仕事を続けることを家族に猛反対され、結局、写真協会にいたのは1年あまり。短い期間でしたが、先輩や仲間にたくさんのことを教わり、濃密な時間でした。「ここは学校でも教習所でもない」とおっしゃった上司にも感謝しています。あの言葉があったからこそ、プロとして恥ずかしくないものを撮らなければと一生懸命頑張れたのだと思います。

後編では約20年間のブランク後に復帰し、102歳の今も撮り続けるのはなぜかをうかがいます。
(後編 5月31日更新予定)
INFORMATION
笹本さんと、2016年に101歳で亡くなったジャーナリスト・むのたけじさんの生き方を見つめたドキュメンタリー映画『笑う101歳×2 笹本恒子 むのたけじ』が2017年6月3日(土)より東京都写真美術館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で公開される。監督はNHKのディレクターとしてドキュメンタリー番組『がん宣告』『シルクロード』『チベット死者の書』などで数々の賞を受賞、大ヒット作『天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ”』で知られる河邑厚徳さん。本作では、むのさんのペンと笹本さんの写真を交錯させながら、二人の証言を通して激しく揺れ動いた時代の人間ドラマを描き出している。

取材・文/泉 彩子 撮影/鈴木慶子
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。