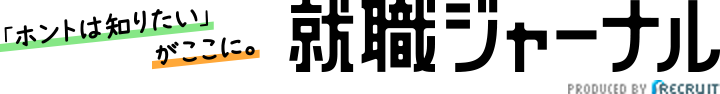たさかひろし・1951年生まれ。1974年、東京大学工学部卒業。1981年、東京大学大学院修了。工学博士(原子力工学)。1987年、米国シンクタンク、Battelle Memorial Institute客員研究員。同時に、米国国立研究所Pacific Northwest National Laboratories客員研究員。1990年、日本総合研究所の設立に参画。民間主導による新産業創造のビジョンと戦略を掲げ、10年間に異業種企業702 社とともに20のコンソーシアムを設立・運営。異業種連合の手法により数々のベンチャー企業と新事業を育成する。取締役・創発戦略センター所長等を歴任。現在、日本総合研究所フェロー。1999年、米国のNew England Complex Systems Instituteのファカルティ就任。2000年、多摩大学大学院教授に就任。社会起業家論を開講。00年、21世紀の社会システムのパラダイム転換をめざすグローバル・シンクタンク、ソフィアバンクを設立。代表に就任。2003年、社会起業家フォーラム(JSEF)を設立。代表に就任。2005年、米国Japan Societyより、US-Japan Innovatorsに選ばれる。08年、ダボス会議を主催するWorld Economic ForumのGlobal Agenda Councilのメンバーに就任。09年、社会起業大学名誉学長に就任。10年、4人のノーベル平和賞受賞者が名誉会員を務める世界賢人会議Club of Budapestの日本代表に就任。11年3月から9月、内閣官房参与として原発事故対策、原子力行政改革、原子力政策転換に取り組む。著書は国内外で100冊余。著書多数。近著に『なぜ、マネジメントが壁に突き当たるのか』『田坂教授、教えてください。これから原発はどうなるのですか?』など。現在、海外でも旺盛な出版と講演の活動を行っている。
知識やスキルだけでは仕事はできない。心の姿勢が問われる
「優秀な若い人間を育てるには、最初に鼻っ柱を叩き折れ」
かつての日本企業では、若い人を育てるに当たって、こんな言葉が受け継がれていました。これから実社会に出る皆さんには、まだ理解できないかもしれません。しかし、ビジネスパーソンとして30年あまり歩んできた今、私にとって、この言葉は有り難く、温かいものとして感じられます。
なぜ、有り難いのか。なぜなら、鼻っ柱の強さ、傲慢さというものは自分ひとりでは気づけないからです。私自身がそうでした。原子力工学で学位を得て30歳で民間企業に就職し、初めて担当した原子力事業のプロジェクトでクライアントにプレゼンテーションをしたときのことです。徹夜で準備をし、自分では最高の企画書を作成してその場に臨んだつもりでした。ところが、私の企画説明を受けたクライアントの部長さんが、烈火のごとく怒ったのです。「こんなものは頼んでいない!」と。
それから後のことは、あまり覚えていません。自分では最善を尽くしたと思っていた企画書を全面否定され、頭の中は真っ白でした。その会社を出て、向かいにある公園に向かって横断歩道を渡っていたとき、同行していた会社の同僚が、私を気づかってこう言ってくれたのです。
「田坂くん、君の企画書は良くできていたよ。あのお客さんに理解する力が無かったんだよ」
その同僚の優しさには、今でも感謝しています。しかし、私の心の中には、違う思いが浮かんでいました。「いや、何が理由であっても、自分は、お客様に納得してもらえる企画が提案できなかったのだ…。それがすべてだ…」という思いでした。
振り返れば、これが私の人生の「分かれ道」だったのかと思います。あのとき、同僚の言葉に、「そうだね。あのお客さんは、専門のことを何も分かっていない。あの企画の意味を理解する力が無いのだね」と答えていたら、私が後に企画の世界で認められ、新たなシンクタンクを創る(つくる)ことも無かったでしょう。企画が受け入れられないことをお客様の責任にせず、「なぜ、お客さまに納得してもらえなかったのか。どうすれば納得してもらえるのか」と自分に問い続けたからこそ、企画プロフェッショナルとしての道を歩むことができた。今はそう思っています。
では、あのクライアントの部長さんは、なぜ、私に対してあれほど怒ったのか。それは、私のどこかに、「自分は専門家なのだから、相手を説得できる」という無意識の傲慢さがあったからだと思います。そのことをあの部長は、敏感に感じ取ったのでしょう。そして、その「鼻っ柱を叩き折って」くれたのです。仕事においては、「知識やスキル」ももちろん大切です。しかし、それだけでは、決して良い仕事はできない。やはり、「心の姿勢」が深く問われる。その大切なことに、あの部長さんが気づかせてくれた。いま振り返っても、あの部長さんには、感謝の気持ちが浮かびます。
そもそも、仕事の世界の素晴らしさは、「下座の行(げざのぎょう)」を務めさせてもらえるところにあります。「下座の行」というのは仏教用語ですが、「誰かに仕えることに徹する」ことを通じて人間成長をめざす行のこと。ただし、それは、「我々(われわれ)はお金をもらっている業者なんだから、お客さんには、無理を言われても一生懸命に仕えるしかない」といった卑屈な意味ではありません。
「下座の行」とは、「下座」に徹して仕え、そのことを通じて自らが成長するという「誇り高き行」です。そして、それは、誰にとっても日々の課題です。例えば、我々がお客さまの会社を訪問し、下座の行をする。その帰り道に、我々が喫茶店に入れば、今度は、喫茶店の主人が我々に仕えるという行をする。その主人が、スーパーマーケットに行けば、今度は、その主人がお客さまで、マーケットの店員が下座の行をする。こうして、我々は、立場を変えながら、日々、人間成長への修行をしているのです。その意味に気がつけば、「仕事」という言葉が「仕える事」と書かれる意味も、「働く」という言葉が「傍(はた)」を「楽(らく)」にするという意味であることも、深く理解できるでしょう。
もとより、「下座の行」とは、ときに苦労や苦痛を伴うものです。今、この人に仕えることが自分にとっての行であると分かっていても、やはり人間には「エゴ」があります。ときに、お客さまの言葉で、プライドを傷つけられるときもある。侮辱を感じるときもある。それでもなお、お客さまの気持ちを感じ取り、お客さまに喜んで頂くために最高の仕事を提供しようと腕を磨く。この行は、決して楽な行ではありませんが、それを通じて、我々は、一人のプロフェッショナルとしても、一人の人間としても、大きく成長していくことができるのです。

実社会の荒波の中でも、社会変革への思いを失わずにいられるか
2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故が起きて間もなく、原子力工学の専門家として、内閣官房参与に就任しました。私は、1990年に日本総合研究所の設立に参画しましたが、それを機に、シンクタンクの仕事に使命感を抱き、原子力の分野から離れた人間です。しかし、それから20年あまり経って、この事故が起こり、総理からの要請で、この事故対策に当たったわけです。私の学位論文は、「核燃料サイクルの環境安全評価」でしたが、それが最悪の現実になることは、かつて想像もしていませんでした。
この内閣官房参与というのは、総理大臣の特別顧問(アドバイザー)という立場ですが、参与として活動した5カ月の間、私は大学の講義や執筆活動など、すべての仕事を休ませて頂き、文字通り早朝から深夜まですべての時間を原発事故への対策と原子力行政の改革に注ぎました。
それは、この分野の専門家として、当時の福島第一原発が予断を許さない極めて厳しい状況であると判断をしたからです。そして、この事故を最悪の事態から回避させることが、かつて原子力に携わってきた人間としての責任だと思ったからです。
そして、内閣官房参与の務めを終え、官邸から大学に戻った後も、私は、原子力行政と原子力産業の抜本的改革を実現するために、政府に働きかけ、メディアを通じて語り続けています。それは、学生時代の若き日に、自分が心に刻んだ一つの思いがあるからです。
私が大学に入った1970年頃は、学生運動が盛んな時代でした。当時の学生は、誰もが「我々(われわれ)が社会を変えるんだ」という思いを持っていました。しかし、この「社会変革」という言葉の意味を取り違え、「革命だ!蜂起だ!」といった扇情的な言葉を語り、大学のバリケード封鎖や機動隊との衝突などの過激な行動に出る学生たちがいたのも事実です。そうした時代の空気の中で、ある日、「全学バリケードストライキ」を主張する学生たちを中心に、クラス討論が持たれました。そのクラス討論において、私自身が語った言葉があります。
「今、言葉で『革命』や『蜂起』を叫び、大学にバリケードを築き、機動隊に投石することは、決して難しいことではない。我々にとって、本当に困難な闘いは、これから30年の闘いではないか。実社会に出たとき、その荒波の中においても、この社会変革への思いを決して失わず30年の歳月を歩めるか。それこそが、最も困難な闘いではないのか」
いま振り返れば、青年らしい青臭い言葉だったかとも思います。未熟な若者が、偉そうなことを言ったかとも思います。しかし、それでも、あの言葉を語って良かった。なぜなら、語った言葉というものは、必ず自分に戻ってくるからです。あの言葉のお陰で、自分は、それからの30年、拙い歩みながら、「社会変革」の志を失うことなく、歩んで来ることができたのでしょう。
大学時代のあの日から、すでに40年。その志は失わずに歩んで来たとの思いはありますが、では、次の世代に胸を張ってバトンを渡せる社会を我々の世代が築いてきたかと自問するならば、まだ、そうとは言えません。私が、大学教授の仕事やシンクタンクの仕事のほかに、2003年に「社会起業家フォーラム」を立ち上げたり、2012年に「デモクラシー2.0イニシアティブ」という新たな民主主義を目指す運動を立ち上げるなど、様々な社会的活動をしているのも、あの日の自らの言葉が、まだ心の中で鳴り響いているからです。
実社会の荒波は、やはり、厳しいものがあります。そして、ビジネスの世界は、生易しい世界ではありません。様々な苦労や困難、挫折や敗北が待ち受けている世界です。私自身も、その苦労や困難、挫折や敗北をいくつも味わってきました。しかし、それでも、申し上げたい。このビジネスの世界は、やはり、素晴らしい世界です。最高の世界です。
なぜなら、志を失わず、使命感を抱き続けて、この世界を歩むならば、我々は、最高の成長を遂げることができるからです。一人のプロフェッショナルとして、一人の人間として、最高の成長を遂げることができる。
そして、その「人間成長」というものこそが、仕事の最高の報酬なのです。もとより、給料や年収、役職や地位というものも、報酬かもしれません。しかし、その報酬は、いつか、儚く(はかなく)消えていく。しかし、「人間としての成長」は、決して失われることのない素晴らしい報酬なのです。
「仕事の最高の報酬は、人間としての成長」。
実社会の荒波の中で、何のために働くのかを見失ったとき、この言葉を思い起こして頂きたい。そして、志と使命感を抱き、高き山の頂に向け、生涯を賭して歩み続けて頂きたい。その山の頂きには、素晴らしい何かが待っています。

INFORMATION
田坂さんの著書には『なぜ、働くのか』『仕事の報酬とは何か』『未来を拓く君たちへ』など、働くことの本質について語ったものが多く、世代を超えてたくさんの読者に支持されている。中でも『仕事の思想 − なぜ我々は働くのか』(PHP研究所/税込み560円)は、単行本の初版発行(1999年)から15年近く経つ現在も読み継がれている良書。「なぜ、我々は働くのか」という深い問いに対し、田坂さん自身のエピソードを交えながら、易しい言葉で語られており、仕事を通して成長する豊かさ、喜びを教えてくれる。

取材・文/泉彩子 撮影/鈴木慶子
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。