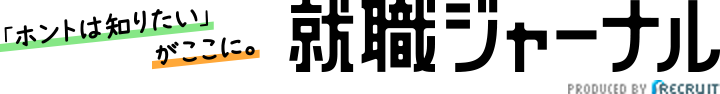2020年5月に上演される赤坂大歌舞伎に出演する中村七之助さん。歌舞伎で何度も上演されてきた『怪談 牡丹燈籠』が、この春、新たな解釈で上演されます。古典を新作として上演する意義とは?そもそも伝統ってどういうこと?そして、幼い頃から舞台に立ち続けている七之助さんにとっての「仕事観」とは―?いろいろうかがってきました。
何をしていても、頭の中に歌舞伎があるんです
―本日は、就活生に向けたお話でうかがいました。
本当ですか!?そんな…就活したこともない歌舞伎役者が何を言っているんだって思われちゃいますよ…皆様、本当にすみません(笑)。
―こちらこそ、すみません(笑)。幼いころから舞台に立っておられますが…。
僕はですね、親の七光で役を頂いて、役をやっていくうちに、父の姿勢やいろいろな先輩の芝居を観て、いつの間にか歌舞伎が大好きになっていて、そのままやっているだけなので、ぜんぶ親のおかげなんです。
―そうやって受け継がれていくところが本当に素敵だなと思います。「仕事」というと、七之助さんはどんなイメージをお持ちですか?
自分のしていることには、いまだに「仕事」という意識はないです。「仕事」っていうと、食べていくために、やらなきゃいけないことっていうイメージなんですよ。僕は好きでやっているので。
―お好きじゃないと、とてもできないことのようにお見受けします。
休みがないですしね(笑)。毎日、昼と夜の公演をして、その間に翌月に演じる4役の稽古をして、それがずっと続いて。好きだからいいけれど、好きじゃなかったらね(笑)。就活生の皆さんは嫌でしょう?ずっと仕事のことを考えているって言ったら。
―とおっしゃると?
常に考えているんですよね、漠然と歌舞伎のことを。いつからそうなっていたのか、もう血に流れている状態だから、自分でもわからないんですけど。楽しいことをして遊んでいる時でも、どこかに絶対ある。それは感覚的にわかります。何だろう…やっぱり生活の一部だからかもしれない。
―どんな感じなんですか?
素敵な景色を見たら、歌舞伎のあの作品のあの場面みたいだなとか。砂の上を歩いた時には、こんな感触なのか、覚えておこうとか。雪が降った日の空気や感覚…そういう日常のちょっとしたことが、全部、歌舞伎に結び付くんです。いい話を聴いたら、芝居になるなと思うし。誰に言われたわけでもなく、自然と頭がそうなっているんだと思います。
大事なのは、先人の考えに触れること
―『牡丹燈籠』には個性の異なる3人の女性が登場します。悪女に定評のある七之助さんですが、演じられる3人の中にも、悪女といっていいような女性が2人出てきますね。
お国とお峰ですね。まだ台本はできていませんが、面白い女性になると思います。お国は悪巧みをするような闇のある、ちょっと妖艶な女性。お峰も人間くさいところがあって。どちらも生きることに懸命で、目的を達成するためには手段を選ばない女性ですから。
―悪役は演じるのが面白いとよくうかがいます。
いいお役は「筋立て」といって、物語の流れを説明するような、言ってみれば損な役割を担うことが多いんです。その点、悪役の方が人間の業やおかしみが描かれやすいんでしょうね。そういうことでいうと、お峰なんて、チャーミングな悪役だと思います。
―5月に上演される『牡丹燈籠』は、新たな解釈の新作だそうですが、歌舞伎で新作を上演する意義については、どうお考えですか?
古典を大事にするのはもちろんですが、その上で新しいことをやり続けることが本来の歌舞伎役者なんじゃないかと僕は思うんです。歌舞伎が生まれ、月日がたって、古典芸能になりましたけれど、江戸時代は全部、新作だったわけですよね。
―本当にそうですね。
面白い作品が生まれて、いろいろな人に上演されながら受け継がれて、古典になったわけですから。脚本を書いた人がドキドキしながら役者に見せて「ここがつまらないな」とか「ここをこうしよう」とか、そういうことで続いてきたのが歌舞伎だと思うので、新作はやり続けるべきだと思います。
―今は、古典も新作も楽しめます。
この時代に生まれたのは、ある意味、とてもラッキーだと思います。もう少し前なら、新作なんてやらせてもらえなかったし、テレビに出ただけで怒られていた時代もありますから。古典にも素晴らしい先輩方が継承してくださったダイヤモンドみたいな作品があり、新作も受け入れてくれる度量がある。素晴らしい時代なんじゃないかなと思います。
―古典と新作ということですと、就活生の皆さんも企業説明会で「伝統と革新」という言葉をよく耳にすると思うんです。普通に生活していると、なかなかピンとこない言葉だと思うのですが。
僕の考え方は、就活中の若い人たちとはもう違うと思うから、大丈夫かな…だって、僕は携帯電話ができる前の世の中の方が良かったなと思っている人間ですから(笑)。
―だいぶ変わりましたね、その前後で。
人と人のコミュニケーションが変わっていった気がするんです。食券を買うのも機械になって、電車の改札も自動になって。それ以前は、切符は駅員さんが切ってくれていたでしょう。「お疲れさま」って言いながら。
―そうですね。
コミュニケーションのあり方が変わっていって、今は大変な時代ですよね。上司が部下を食事に誘っちゃいけないんでしょう。でも僕は、先輩との食事は行った方がいいと思うんですよね。
―とおっしゃると?
同じ職業だったら、いろいろな話を聴けるかもしれないじゃないですか。仕事とプライベートは分けたいっていう人もいるかもしれないけど、プライベートだって仕事に結び付くと思うんですよ。何か具体的に結び付かなくても、信頼は生まれるから。プラスには絶対なると思うんです。
―本当ですね。
自分のモチベーションひとつだと思うんです。上の世代から学ぼうとするというのは。学ぶことは絶対にあるから。ダメな人なら、いかにそのダメな人から学ぼうとするか。うわぁすごいな、この先輩……って(笑)。
―すごいなぁとか、こんな考え方もあるのかとか。
それが伝統なんじゃないですか。自分より先に生まれた人の考え方を知る。共感できなくても、聞くだけでもいいと思うんです。そういう考え方があるんだとわかるだけでも、勉強になると思うから。

より複雑な人間模様が楽しめる、新解釈の『牡丹燈籠』
―ところで、七之助さんは昨年、出演されたドラマ『令和元年版 怪談牡丹燈籠 Beauty&Fear』にも出演されています。
歌舞伎の『牡丹燈籠』は本当によくできた脚本で、役者で見せる部分が強いんです。ただ、重要な役でありながら、ほとんど描かれない人物もいるんですね。そこはお客様の想像に委ねる形になっているのですが、ドラマでは、そういう人物にも光が当っているんです。
―今回の歌舞伎は、ドラマと同じ源孝志さんが脚本・演出なんですね。
そうなんです。ドラマの脚本では、そういう人物も含んだ因果応報がより深く描かれていて。男女の因縁だけでなく、親子や師弟関係…全部が入り乱れていて、また新たな面白さがあるなと思いました。
―源さんは、歌舞伎の演出は初めてだそうですね。
源監督から見たら、僕たちが当たり前にやっていることが新鮮に見えることもあると思うんです。新たな角度から見ていただくことで、これまでの殻を破れるところがあるんじゃないかと。源監督が「歌舞伎はそんなに観ていないので不安です」とおっしゃっていたので、こちらからも「歌舞伎では、こういう表現がありますよ」と、稽古でいろいろお見せしていけたらと思います。
―歌舞伎で何度も演じられている演目という点では、いかがですか?
あまり固めずにやれたらと思います。なかなか難しいんですけどね、歌舞伎の『牡丹燈籠』が体に染みついているので。そういう意味では、歌舞伎ではほとんど描かれていないお国がいちばん作りやすいと思います。そこは楽しみですね。
―ほかにも、これまでの歌舞伎とは違う表現が興味深いです。『牡丹燈籠』というと、愛する人に焦がれながら亡くなった若い娘が、死んだ後も現れる怪談として知られていますが、亡くなる場面がドラマではリアルに描かれていました。今回はどんな表現になるのか、気になります。
「焦がれ死に」の場面ですね。歌舞伎では語りだけで、次に現れた時にはもう幽霊になっていて、直接は見せないんです。そこを今回は見せるのか。見せるとしたら、どんな方法がいいのか。舞踊で表現するとしても、歌舞伎は本当に表現の幅が広いんです。そこは歌舞伎のすごいところだなとあらためて思います。そのあたりは稽古場で話し合いたいですね。
―昨年、『風の谷のナウシカ』が歌舞伎になって話題になりましたが、舞台裏のドキュメンタリーを拝見したら、初日まで間もない状態で、七之助さんがお稽古に入られて、大きく演出が変わったところが紹介されていました。そういうアイデアはぱっと浮かばれるんですか。
あれは稽古に入った時に、この方がいいなと感覚的に思っただけです。本当はタブーなんですよ。演出家がいる作品で、役者が提案するというのは。ただ、あの時は超大作で、初日まで時間もなくて、皆が荒野にいるような状態でしたから、演出の方に助け舟を出させていただいて、そのアイデアがたまたま通っただけで。決定権は演出家の方にありますからね。
―お父様(十八代目中村勘三郎)も、この「赤坂大歌舞伎」を始められたり、いろいろな活動をされていましたが、七之助さんもこれから新たな場を作られたり、役者さんのみならず、全体を見据えたご活動をやっていかれるのだろうと楽しみです。
演出は、いつかはしてみたいと思いますけどね。おいそれとできるものではないので、どうなるかわからないですけど。

緊張しない人なんて、ロクな人じゃないですから(笑)
―昨年のNHK大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~』では落語家のお役をやっておられましたね。
落語家という職業を本当に尊敬しましたね。歌舞伎は相手役さんもいますし、小道具も衣装もありますし、顔も頭も普段の自分とは違うじゃないですか。落語家は本人のまま、たったひとりで出ていって、しかも「さあ笑わせてみろ」というお客様の前でやるわけでしょう。図太くないとできないと思います。実際にやってみると、まあ震えますよね(笑)。
―本人のまま、大勢の前に出ていくという点では、就活の面接も、ちょっと似たところがあるかもしれません。
そういう経験、僕もありますよ。歌舞伎には、名題試験という試験があるんです。もう亡くなりましたけれど、(中村)雀右衛門のおじ様を筆頭に、うちの祖父、(尾上)菊五郎のおじ様、全員が1列に並んでいて。そこで、ひとつ何か披露しなさいと言われるんです。結局、僕は披露しなかったですけど。
―とおっしゃると?
「やらせてください」と2回言ったんですけど、「これから見ていくから大丈夫ですよ」って。でも、父には「お前、絶対やれよ」って言われていたので、その時に父を見たら、すごい目で僕を見ていました(笑)。
―それは何歳の時なんですか。
10代の時ですね。入り口から3メートルぐらいのところに皆さんが一列に並んでいるんですけど、自分の席に着くまでの、その距離が人生でいちばん長かったです。緊張しすぎて、大変でした(笑)。
―そういう状況って、どうしたらいいんでしょうね。
もうしょうがないですよね。そういう面接でいいようにしようと思わないことだと思います。だってしょせん、作った自分ですから。もうしょうがないと思って、やることをやるしかないです。そこで緊張しない人間なんて、ロクな人間じゃないでしょ(笑)。だから、緊張していいんじゃないの?って僕は思います。
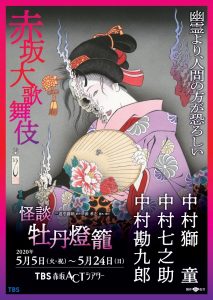 2008年に始まった赤坂大歌舞伎の第6回公演。歌舞伎界の今後を担う3人の人気役者がそろい、昨年のドラマ『令和元年版 怪談牡丹燈籠 Beauty&Fear』(NHK-BS)を手掛けた源孝志を脚本・演出に迎え、新たな解釈の『牡丹燈籠』が描かれる。歌舞伎の『牡丹燈籠』の元となった三遊亭圓朝の長編落語の複雑な愛憎の世界に立ち返り、どんな人間模様が展開するのか―。男女の愛憎のみならず、策略あり、忠義あり、その根底には人の欲望が絶えずあり…多くの人の知る『牡丹燈籠』の面白さと怖さが、新たな角度から見えてくるはずだ。
2008年に始まった赤坂大歌舞伎の第6回公演。歌舞伎界の今後を担う3人の人気役者がそろい、昨年のドラマ『令和元年版 怪談牡丹燈籠 Beauty&Fear』(NHK-BS)を手掛けた源孝志を脚本・演出に迎え、新たな解釈の『牡丹燈籠』が描かれる。歌舞伎の『牡丹燈籠』の元となった三遊亭圓朝の長編落語の複雑な愛憎の世界に立ち返り、どんな人間模様が展開するのか―。男女の愛憎のみならず、策略あり、忠義あり、その根底には人の欲望が絶えずあり…多くの人の知る『牡丹燈籠』の面白さと怖さが、新たな角度から見えてくるはずだ。
原作:三遊亭圓朝 脚本・演出:源孝志
出演:中村獅童、中村勘九郎、中村七之助、山口馬木也、木場勝己ほか
2020年5月5日(火・祝)~5月24日(日)
TBS赤坂ACTシアター
取材・文:多賀谷浩子
撮影:八木虎造
ヘアメイク:中村優希子(Feliz Hair)
スタイリスト:寺田邦子
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。