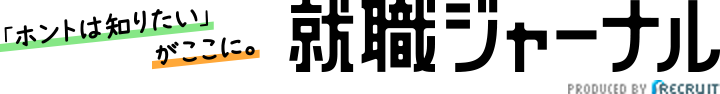こまつなるみ・1962年神奈川県横浜市生まれ。専門学校で広告を学び、82年毎日広告社へ入社。その後、放送局勤務などを経て、90年より本格的に執筆を開始。スポーツ、映画、音楽、芸術、旅、歴史など主題は多岐にわたる。女性では数少なかったスポーツノンフィクションに新境地を開き、また歌舞伎をはじめとした古典芸能や西洋美術、歴史などにも造詣が深い。主な著書に『横綱白鵬 試練の山を越えて はるかなる頂へ』(学研教育出版/税抜き1300円)、『逃げない―13人のプロの生き方』(産経新聞出版/税抜き1600円)などのほか、自身の半生と仕事観を書いた『対話力 私はなぜそう問いかけたのか』(筑摩書房/税抜き700円)がある。
「大きな失敗」から生まれた、一生を懸けられる仕事との出合い
私は、ノンフィクション作家として活動しています。今はスポーツ、映画、音楽、芸術、旅、歴史などさまざまなテーマで書いていますが、原点はノンフィクションのスポーツライターです。1989年、当時27歳。まったくの未経験でこの世界に飛び込みました。
当時は、そもそもスポーツライターという仕事は「専門知識を持った男性がするもの」という風潮がありました。スポーツにもたくさんの種類があります。それぞれの方が自分の得意分野を持ち、人脈を作り、専門的な知識を生かして取材をしていました。それは今も変わらないと思います。人脈も得意分野もないにもかかわらず、しかも女性でこの仕事をしている人はほとんどいませんでした。なぜ何の経験もない女性の私が、男社会だったスポーツライターという未知の世界に飛び込むことになったのか。それは、私が若いころに「大きな失敗」をしたからです。
幼いころから私は本を読むことが好きでした。ジャンルもさまざまでしたし、日本だけでなく海外の作品も興味のあるものを手当たり次第に読んでいました。なぜ本が好きだったのか。その物語を読んでいるときには、実際にはできない体験をすることができます。違う人生を垣間見ることができるからです。イマジネーションで時空を簡単に越えられることを知り、文字で書かれた「人間の可能性」にワクワクしていました。
中学、高校時代の私は、友人たちと楽しい時間を過ごしていました。でも、自分の熱中できるものをいつも求めていましたし、興味のあることにしか集中できないタイプでした。また偏差値という数字だけで評価されることに疑問を持っていたのです。受験勉強というものに「なんの役に立つのか」という不安や不満を抱えていながらですから、集中できず、希望の大学に落ちました。大学に進学しなければならないと思いましたが、浪人することもぜず、結局は、受かった別の大学へ行くことも辞めてしまいました。受験というものは、誰にとっても、初めて客観的な評価をされる機会でもあります。この失敗は、私にとっての最初の挫折でした。大学受験は自分と向き合う機会でもありました。なぜうまくいかなかったのか。興味あるものにしか真剣になれなかった自分を自覚したのもこの時。興味がないまま、学費を払ってもらうことが両親に申し訳ないと思っていました。
大学へ行くのを辞めてしまった私は、石岡瑛子さんというグラフィックデザイナーの方に憧れて「私も広告の勉強をしよう」と思い立ち、広告の専門学校に入りました。その後に勤務した広告会社ではOLとして3年間社会のイロハを教わりました。入社したての新人だからこそ許されていたことも、若い女性だからかわいがってもらえたこともあり、楽しいこともたくさんありました。その中で同期の男性が大きなプロジェクトを任されるようになる一方で、女性の多くは寿退社を考え出していました。この会社員時代に、男女の格差など社会の厳しい現実を知りました。
男性ほど大きな仕事ができない。結婚にもまだ興味がない。「これから自分は何をしていけばいいのか」と悩んでいた23歳の夏、ある人の紹介でTBSの報道部に契約社員として入社することになりました。ちょうど御巣鷹山の日本航空機墜落事故の直後。またアメリカのスペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故などを、同じ年ごろの記者が取材していました。私の仕事は事務職でしたが、そうした事件や事故における報道の在り方について記者の人たちと毎日のように話す中で、「この環境で自分に何ができるだろうか」と真剣に考え始めました。
報道に興味を持った私に「入社試験を受けて記者を目指したら」とアドバイスがありましたが、そこで正社員として入社試験を受けるには4年制大学を卒業していないことがネックになることに気づかされました。
大学へ行くのを辞めてしまった私は、取り返しのつかない過ちをおかしたのではないか、なぜキャリアを積むことを10代のころから真剣考えなかったのか。 そう考え続け、悩んでいるうちに自律神経失調症になり、3カ月ほど自宅療養することに。今後の方向性について考え抜くうちに「自力で何とかしよう。自分の好きなことをやろう」と決心したのです。これなら誰に対しても言い訳できませんし、一生逃げずにやり遂げられるはず。そう思いました。
仕事を辞めた後、アルバイトをしながらいろいろな職業に触れるなかで、「そもそも自分が好きなもの、極めたいものは何だろう」と考え、すべてのことを教わった「本」の存在にたどり着きました。「本を書く側になろう」「自分で原稿を書いて食べていこう」と思い、27歳でライターを目指すことになったのです。
今では「あの悩んで苦しんだ時間は、この仕事に出合うためだったんだ」と思えるようになりました。何も悩まなければ、何も考えずに別の人生を送っていたかもしれません。その意味で、失敗というのは本当にありがたいと思います。
「失敗こそ絶好のチャンス」。何も持っていない裸の自分に向き合い、何を身につけ、どう進んでいくか。それは失敗したときにしか考えられません。自分は何がやりたいのか、何ができるのか、それを考えぬく時間を持てたことがライターという仕事に出合うきっかけでした。必ずそういう経験は人生のロードマップになります。

「人間を描きたい」と憧れ、ライターの道を突き進んだ
ライターになるため執筆の仕事を探していたころ、知人に『Hanako』(マガジンハウス)という生活情報誌のアルバイトを紹介してもらい、お店紹介を担当させてもらいました。その仕事を頑張る一方で、これまでさまざまな本や映画を見て、そこで繰り広げられる壮大なドラマ、またささやかな日常に心を動かされ、「いつかは『人間』というテーマについて描きたい」と思っていました。当時はバブル真っ盛り、スポーツ選手がヒーローとして脚光を浴びていた時代です。『Number』(文藝春秋)というスポーツ雑誌に執筆していた沢木耕太郎さんや山際淳司さんといったノンフィクション作家に憧れ、「この媒体でスポーツノンフィクションの仕事をしてみたい」と編集部に売り込みました。
最初は実績が少なく、まったく相手にしてもらえませんでしたが、幸運にも以前働いていたTBSの上司だった方に、当時編集長の設楽敦生さんを紹介していただきました。初めのころは文章を何度書いても、編集担当者に「つまらない」と突き返され、陰で泣きながら書き直したことも度々あります。しかし、苦しんで悩んで、やっと見つけた自分のやりたいことです。自分で選んだ仕事です。「自分ならやれる」と自分を信じていました。信じて突き進むしかなかったという方が正確かもしれません。そのうち「小松さんの思いがちゃんと文章に込められているね」と言われるようになり、文章を書くのがだんだん面白くなってきたのです。
人生の転機となったのは、90年に近鉄バッファローズでプロ野球デビューした野茂英雄さんの取材でした。当時は新人ながら、「トルネード投法」を武器に最多勝利・最優秀防御率・最多奪三振・最高勝率と投手四冠を独占し、ベストナイン・新人王・沢村賞・MVPにも輝いたすばらしい投手です。その後は日本人として史上2人目のメジャーリーガーとして活躍しました。その野茂さんを取材したのは91年、デビュー2年目のころ。ヒーローから何を聞き、どう書くか。ライター3年目の私にとっては最大の難関でした。その原稿を設楽さんが褒めてくださり、仕事の幅も広がって、ようやくスポーツノンフィクションライターとしての一歩を踏み出せたのです。
私は「自分の本を出版したい」と思っていました。最初に書いた本は『アストリット・Kの存在 ビートルズが愛した女』(世界文化社)です。1960年代に活躍し、今でも多くのファンに愛されているロックバンドのビートルズ。その初期メンバーでジョン・レノンの親友でもあったスチュアート・サトクリフという人がいて、その恋人だった写真家の女性がアスリット・キルヒヘアです。
彼女の青春を描いた映画が公開される直前、ある雑誌の企画で世界初の試写を見る機会を得て、そこで「彼女をテーマに本を書きたい」と強く思ったのです。1年半もの間、毎週のように何度も中学生レベルの英文で手紙を書き続けました。ようやくアスリットに会えましたが、私の質問の仕方がつたなかったせいか、途中でインタビューを打ち切られたこともありました。
私の仕事で最も大切な「取材」という行為は、ものすごくエゴイスティックなものだと思います。名刺1枚を交換しただけで、「あなたの人生をすべて話してください」というわけですから。だからこそ、絶対に礼節を失ってはいけないと思います。向き合う人間に対して自制心を持ち、礼儀をまっとうできるかを常に自分に問いかけ続けています。これは今でも変わりません。取材対象の人とは、決して友達のようにはなれません。向き合う人間と自分との間には、すごく大きく深い川が流れているという意識がいつもあります。
相手の踏み込んではいけないものを知ること、自分との距離を意識すること、それが相手を知りたいという強い思いにつながるのだと思っています。
そして、ようやく大きな目標だったスポーツ選手の本を書くことができました。サッカー選手で2006年FIFAワールドカップまで日本代表として活躍した中田英寿さんに取材する機会を得て、『中田英寿 鼓動』(幻冬舎文庫/724円)など彼に関する本を何冊も執筆。そして、今も米国メジャーリーグのヤンキースで活躍しているイチロー選手を取材し、『イチロー・オン・イチロー』(新潮社)を書きました。
当時は活躍するアスリートの「生の声」を伝えるような作品が少なく、「私がスポーツ選手の取材を通じて受けてきた勇気や希望をたくさんの人たちに伝えたい」というのが、一人の人間の半生を描いたこれまでの著作に共通する思いです。
私はこの仕事を始めてから、自分が興味があること、好きなことしかやってきませんでした。好きだからこそ、情熱が持てるし、それは相手にも伝わります。今、この瞬間も「今日が一番楽しい」と思っています。スポーツも、歌舞伎も、今まで向き合ってきたテーマは何もかもすべて大好きです。そして、なにより、人間が大好きです。人間は、素晴らしく、慈悲深くて尊い。しかし、残忍でずるい。これほど不思議な存在はいないでしょう。仕事でも、プライベートでも、向き合う人のことを、光の部分も影の部分も含めてすべて受け止めたいという思いは、今もこれからも決して変わりません。
どんなに取材をたくさんし、本を出しても、「慣れる」ことはありません。相手の思いや人生を考え、その生き方や人生観に共感し、泣きながら執筆することもたびたびあります。取材をするとき、本を書くとき、その話を聞かせてくれたことに感謝し、「相手の人生を背負う覚悟が私にはあるのか」と常に客観的に、自分に問うています。

INFORMATION
『横綱白鵬 試練の山を越えて はるかなる頂へ』(学研教育出版/税抜き1300円)は、日本の伝統である相撲を若い世代に伝える手段として本が一番良いだろうと、白鵬関自身が執筆者として小松さんを指名したという。角界の諸問題などで相撲人気に陰りが見え、日本人の心が相撲から離れるなか、命を賭して土俵に立つ白鵬関の生き様に見える、何事にもくじけない心を持つことの大切さがわかりやすい筆致で描かれている。

取材・文/大根田康介 撮影/鈴木慶子
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。