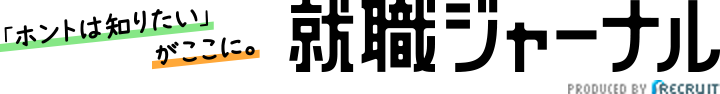自動車業界に興味があっても「どんなビジネスモデルがあるのかよくわからない」「やりがいや仕事内容の違いは?」「将来性はある?今後の動向が知りたい」と悩んでいる人もいるでしょう。
そこで今回は、リクナビ就職エージェントのリクルーティングアドバイザー(※)が、自動車業界のビジネスや仕事のやりがい・魅力、現状や今後の展望・将来性、志望動機の書き方のポイントまで解説していきます。業界研究や応募書類の作成などの参考にしてみましょう。
※リクルーティングアドバイザーは求人を出す企業の採用サポートを行う。
目次
自動車業界の仕組み
まずは自動車業界の仕組みを紹介します。
自動車業界とは、自動車メーカー、部品メーカー、素材メーカー、販売会社など、自動車の製造・販売に関連する業界を指します。
いわゆる自動車メーカーとは、車、バイク、バス、トラックなども含めた完成車の製造・販売を手がけている完成車メーカーのことを指しますが、これらの完成車には何万点もの部品が使われており、部品メーカーがその製造・販売を手がけています。
完成車メーカー、部品メーカーはどちらもグローバルに販売を行うケースが多く、ほかの業界のメーカーと比較すると、海外売り上げの比率が高い点も特徴と言えます。
一方、素材メーカーは自動車製造に必要な素材の製造・販売を行い、販売会社は自動車メーカーから仕入れた完成車を一般ユーザーに販売しています。また、完成車の販売網は、メーカー別ではなく、ブランド別に分かれているケースも多く、関連会社や子会社、孫会社など、数多くの企業が自動車販売にかかわっています。
そのほか、自動車の修理・整備や、レンタカー、カーシェア、自動運転の精密機器など、自動車に関連した各種サービスを取り扱う企業も、自動車業界に含まれるという見方もあります。
自動車関連産業の就業人口は554万人(※)に上っており、自動車産業は「日本の経済を支える重要な基幹産業」とされています。
※ 出典:「日本の自動車工業2023」(一般社団法人日本自動車工業会)
自動車業界のビジネスモデル
ここでは、自動車業界の代表的なビジネスモデルについて紹介します。
完成車メーカー
一般的に「自動車メーカー」と称されているのが「完成車メーカー」であり、素材メーカーや部品メーカーなどから仕入れた部品を、完成車に組み立てるメーカーのことを指します。
日本の大手自動車メーカーは数社しかありませんが、ここから各種部品を受注する部品メーカーは数千社にも上っており、自動車業界の屋台骨を支えていると言えるでしょう。
財務省発表の「令和5年分貿易統計(速報)の概要」(※1)によると、自動車は、輸出金額における増加品目の中でもトップの伸び率となっています。
輸出台数においては、近年、感染症の流行や半導体不足、さまざまな世界情勢の変化による影響で減少に転じるも、2023年以降は復調傾向にあり、世界トップ3を保ち続けています(※2)。
このように、完成車メーカーを中心とする日本の自動車産業は、世界に誇るグローバル産業でもあるのです。
※ 出典1:令和5年分貿易統計(速報)の概要│財務省
※ 出典2:2024年1月11日付 今週の指標 No.1329│内閣府
自動車部品メーカー
自動車1台を組み立てるためには、小さなねじも含めて約2~3万点以上の部品が使われるとされています。こうした部品類は、大小の自動車部品メーカーが手がけており、自動車部分品・付属品、内燃機関電装品まで含めると、少なくとも6000社近い企業があります(※)。
部品メーカーには大きく2つの分類があり、自動車メーカーと直接取引で部品を供給している場合は「ティア1(Tier 1)」ティア1メーカーに部品を供給している場合は「ティア2(Tier 2)」と呼ばれます。
※出典:全国5849社「自動車部品メーカー」業績動向調査 売上は2兆5,000億円減、コロナ禍で落ち込み拡大│東京商工リサーチ
かつては、特定の自動車メーカーのみと取引する方式が主流となっていましたが、昨今は、複数の自動車メーカーと取引する部品メーカーも増えています。
また、海外部品メーカーとの競争が激化している昨今は、特定の専門分野においてトータルの提案をすることで、競合優位性を高める動きも出てきています。1つの部品だけでなく、例えば、エンジン周りやエアコン周りの構成に必要な部品群をユニット形式で提供するケースなどがこれに当たります。
さらに、自動運転技術や、カーナビなどに関連するGPSや地図システムなどの開発を手がける部品メーカーなども登場しています。
日本の自動車部品メーカーには、2023年時点で世界第2位の売り上げ規模を誇る企業や、特定領域の部品で世界トップシェアを獲得している企業なども複数あり、高い技術力を持っています。
自動車販売会社(カーディーラー)
自動車販売会社(カーディーラー)は、完成車メーカーから完成車を仕入れ、その販売とアフターサービスを手がけています。
完成車を手がける自動車メーカーごとに販売網が整備されており、系列店である自動車販売会社は、基本的に他社の車を取り扱うことはありません。
自動車メーカー内でもブランドごとに販売網が分かれ、特定のブランドの車種のみを扱うケースがほとんどでしたが、昨今では統廃合が進み、取引メーカーのブランドをすべて取り扱い、幅広い提案を行うケースも増えています。
その一方で、一つの高級車ブランドに特化した販売・サービスを手がけ、富裕層の顧客獲得に特化する自動車販売会社も登場しています。
また、特定の自動車メーカーの系列に入ることなく、複数メーカーの車を取り扱う個人ディーラーもあり、こちらは、営業職・整備士などの少人数で構成されていることも多いでしょう。最近は、中古車だけでなく、新車のインターネット販売が台頭しています。
そのほかの自動車関連メーカー(素材メーカー・タイヤメーカー)
自動車製造にはさまざまな素材が使われており、車体などに使用する普通鋼、ラジエーター(エンジンを冷却する部品)などに使用する銅、ホイールなどに使用するアルミニウムだけでなく、そのほか、プラスチック、ゴム、ガラス、塗料など多岐にわたります。それぞれの素材を扱うメーカーがあり、より自動車製造に適している材料の開発に尽力しています。
一方、タイヤメーカーは天然ゴムなどの原材料を仕入れ、自動車、バイク、トラック、バスなど、さまざまな車両の種類に応じたタイヤの製造・供給を手がけています。タイヤメーカーでは、自転車や航空機に使用するタイヤなども展開していますが、ビジネスの比重としては自動車関連が多くを占めており、自動車の販売台数に業績を左右されてしまうほど、自動車業界と深くかかわっています。
また、どちらのメーカーにおいても、昨今は電気自動車に対応するために、樹脂による軽量化素材や、タイヤの開発などに注力する傾向も見られます。
自動車関連サービス(修理・整備、カー用品、カーシェアリングなど)
自動車業界には、商品販売後に関連サービスを提供する企業も多く、自動車の修理・整備、パンク・故障時のロードサービス、各種カー用品の販売、中古車販売などのサービス事業はアフターマーケットと呼ばれています。
また、自動車を所有せず、必要なときのみ利用できるサービスとして、レンタカー、カーリース、カーシェアリングなどもあります。最近では、大手自動車メーカーもカーシェアリング事業に乗り出しており、自動車利用の新たな選択肢として、今後も伸びていくことが期待されています。

自動車業界で働く魅力とやりがい
ここでは、自動車業界で働く魅力とやりがい、完成車メーカーと部品メーカーのやりがいの違いについて解説します。
グローバルに影響力を持つ製品に携われる
日本にはさまざまな製品のメーカーがありますが、世界中で利用されているケースはそれほど多くないものです。自動車業界のメーカーで働く場合は、自分が携わった製品が世界各地で利用されるため、影響力の大きさにやりがいを感じることができます。
また、自動車産業は日本の経済を支える主要産業であり、大手自動車メーカーなどのニュースが大きく取り上げられるなど、世間の注目を集めることも少なくありません。世界に誇る産業である自動車業界を内側から支えていくことに誇りを感じることもできるでしょう。
かかわった製品が身近で利用されている
自動車は目に見える「形」になるものであり、かつ、日常的に多くの人が利用しているものです。街を歩いていても、自分がかかわった製品が利用されている様子を見かけることは少なくないでしょう。
特に、メーカーで働く場合は、ものづくりに携わる醍醐味(だいごみ)を味わうことができます。また、販売会社や関連サービスに携わっている場合でも、自分が取り扱っている車やサービスを周囲の人が利用していることで、身近な場所で役立っている様子を感じられるでしょう。
人生の大事な買い物で選んでもらえる
人生における買い物の中で、自動車は、住宅の次に高価な商品と言えます。多くの場合、大きな買い物になればなるほど、思い入れを持って購入の決断をするものでしょう。
人生において大事な買い物をする際に、自分のかかわった商品を選んでもらえる喜びは、自動車業界で働く人が感じている魅力の一つと言えます。販売会社の場合は、購入機会に直接かかわり、自分の提案力によって選んでもらえるという、さらに大きな喜びを味わえるでしょう。
社会インフラを支える使命感を味わえる
自動車は、公共交通機関や物流などにおいても重要な役割を担っており、また、地方都市においては必要不可欠な交通手段と言えます。現在、社会インフラを支えるものとなっているため、自動車業界では、世の中に貢献する使命感を実感している人も少なくはありません。
今後、高齢社会が進んでいく中では、自動運転などの先端技術が求められることが予想されます。
また、電気自動車についても、環境に貢献できるのみでなく、蓄電池そのものを電力として利用することができます。災害対策や発電の効率化などにも利用できるため、そうした面から社会インフラに貢献していく未来も予想されています。
完成車メーカーと自動車部品メーカーの違い
自動車業界に興味を持っている人は、メーカーを第1志望とするケースが少なくありません。その際、「完成車メーカーと自動車部品メーカーのどちらを選べばいいのか」と迷う人もいるでしょう。
完成車メーカーは、最終的な製品の製造を手がけているため、BtoC(※1)のビジネスとしての魅力を感じるケースが多いと言えます。特に、開発や製造にかかわる職種の場合、自分で考えて作り込んだものが世の中に出て、エンドユーザーの人々に直接利用される喜びを実感できます。入社後、かかわれる車種のブランドが限られてくるため、特定の領域で技術力を高めたり、特定の製品を追求していくやりがいもあるでしょう。
一方、自動車部品メーカーは、完成車メーカーと取引するBtoB(※2)のビジネスが基本です。完成車メーカーの開発・製造部門と一緒に、どのようなものを目指すのかを考え、検証・改善を繰り返していきます。PDCAサイクル(※3)を回しながらより良いものを作ることにやりがいを感じている人も多いでしょう。自動車部品メーカーで開発・製造などを手がけている場合は、さまざまなブランドの車種に携わることが多く、幅広いメーカーの開発・製造にかかわるケースもあります。多様な開発・製造に携わる楽しさも魅力と言えるでしょう。
これらの違いを理解した上で、「自分のやりたいことにマッチしているか、強みを発揮できるか」をしっかりと考えることが大事です。
※1「Business to Customer」の略。企業がモノやサービスを個人(一般ユーザー)に提供するビジネスモデルのこと。
※2「Business to Business」 の略。企業が企業に対してモノやサービスを提供するビジネスモデルのこと。
※3 PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのプロセスを繰り返し行うことで、継続的に業務改善や業務効率化を目指すフレームワークのこと。
自動車業界のランキング・年収・待遇・社風などの調べ方
自動車業界のメーカー各社の業績、年収などについては、『会社四季報』(東洋経済新報社刊行)に掲載されています。業界ランキングやトレンドなどは、業界地図として、各業界の動向を詳細に解説している本で確認することができるでしょう。
大企業の場合は、ホームページや採用ページの情報が充実していることも多いので、社風や仕事内容、キャリアパスなどの情報収集に役立てることができます。待遇や社風、年収の実態などが知りたい場合は、企業の口コミサイトを調べる方法もあります。
また、自動車産業は規模が大きいため、身近な人が働いているケースも少なくはないでしょう。自分で情報を収集するだけでなく、実際に働いている人に、直接、話を聞いてみることもおススメです。周囲に見当たらない場合でも、友人・知人などに聞いてみれば、紹介してもらえる可能性もあるでしょう。
自動車業界に向いている人とは?
ここでは、自動車業界に向いている人の特徴について解説します。
ものづくりが好き
自動車産業は、日本を代表するものづくり産業の一つと言えます。また、電気自動車や自動運転などをはじめ、新たな技術に取り組み続けている業界でもあります。ものづくりが好きな人や、技術革新に興味がある人には向いているでしょう。
社会インフラを支えたい
先にも述べた通り、自動車業界は交通や物流など、社会インフラを支えています。また、少子高齢化が進む社会を支えるために、自動運転技術の実用化などにも期待が集まっています。社会インフラを支える使命感を味わいたい人にとっても向いていると言えます。
新規事業や海外での活躍に挑戦したい
自動車業界では、ゼロからものづくりに取り組み、新たな技術の開発や海外事業の展開などにも注力している企業も多くあります。新規事業やグローバルなフィールドなど、知らない世界にも物おじすることなく興味を持って飛び込み、成長していきたいという人には向いていると言えるでしょう。
特に、完成車メーカーの場合は、海外事業も積極展開していることが多いため、バイタリティーやチャレンジ精神がある人材を求める傾向があります。
コツコツ積み重ねていくことが得意
ものづくりにおいては、地道な作業を一つひとつ重ねていくことが必要です。小さな課題にもいちずに向き合い、コツコツ積み重ねていくことが得意な人や、物事を改善していくことに喜びを感じる人に向いていると言えるでしょう。
特に、自動車部品メーカーの場合は、完成車メーカーの自動車製造を技術力で支える側面が強くあるため、難しい要望もクリアしていく根気強さが求められるでしょう。
理系の知識が必要な技術職種の場合は?
技術職種の場合は、学生時代の専攻分野なども関係してくるでしょう。電気・数学・機械系の学部の場合は、自動車業界の開発・製造などに必要な知識を学んでいるため、素養があると言えます。
また、昨今は自動運転などの技術開発にも注力しているため、情報系の学部で学んでいる場合、AI活用なども含めた先端技術の開発を担う素養があると言えます。
いずれの場合も、ものづくりの現場で活躍したいという人には向いているでしょう。
自動車業界の主な職種と仕事内容
自動車業界の主な職種について、それぞれの仕事内容を解説していきます。
研究開発職
電子技術、モーター、エンジン、トランスミッションなど、多様な技術領域の研究・開発、生産技術の向上などを手がけるスペシャリストです。それぞれの技術領域ごとに、求められる専門知識やスキルなども異なります。
また、5年、10年先などの未来を見据え、次世代自動車にかかわる研究・開発も行っています。例えば、自動運転技術や電気自動車、ハイブリッド車などがこれに当たります。先端技術の研究・開発については、ほかの業界と比較して長いスパンで取り組む傾向があるでしょう。
生産管理・生産技術職
生産管理職は、需要に応じた生産計画を立て、部品調達や工場ラインによる自動車生産量の調整、納期に合わせた生産管理を担当します。
一方、生産技術職は、生産のプロセス設計や生産体制の改善・向上、新規生産ラインの立ち上げなどに携わります。研究・開発部門や設計部門と製造現場をつなぎ、業務内容や人員配置の見直しなども手がけます。このほか、生産にかかわる職種としては、製品の品質を管理する品質管理などもあります。
生産関連の職種の場合、海外拠点の工場の立ち上げや現地スタッフの指導を担うなど、グローバルに活躍できるケースもあります。また、理系だけでなく、文系出身者が担当するケースも少なくはありません。
事業企画職
職種や部署によっても業務は異なり、新車の企画やコンセプトの立案、営業企画、マーケティング、消費者動向調査、資材や部品の調達、物流・生産企画、販売促進、海外事業支援などさまざまです。
いずれの場合も、新車や既存車両に関連する各種企画に携わり、自社のブランドイメージを大切にしながら、ユーザーのニーズや、購買ターゲット、商品のアピールポイントなどを考えるクリエーティブな仕事と言えます。
営業職(完成車メーカーの場合)
完成車メーカーの場合は、ディーラーへの営業支援を行います。自社の自動車の特徴を競合他社の類似車種と比較の上、接客販売に役立つ情報を提供するなどで販売・販促活動をサポートします。ディーラーの営業販売数字の管理に加え、店舗ディスプレー、キャンペーン・イベントの企画なども協力して行います。
また、企業や官公庁に向けた営業活動も担当します。大口取引となるため、自ら提案活動を行い、取引における入札なども手がけます。
営業職(部品メーカーの場合)
完成車メーカーへの営業活動を行い、部品供給の案件を獲得します。また、新しい車種の開発には約3年の期間を要するものなので、新規の自動車開発案件を獲得するために、形状や搭載したい機能などの要望を引き出し、社内開発部門と一緒に検討した上で、仕様や価格などの提案を行います。
バックオフィス業務
バックオフィスとは、総務、経理、財務、人事、労務などの総称で、管理部門やコーポレート職、スタッフ職などと呼ばれることもあります。
担当する領域を通じて、社内のあらゆる部署とかかわりながら、各署の業務をバックアップします。
グローバル展開している企業の場合は、社員の規模が数万人に上ることもあり、仕事のスケール感も大きくなる可能性があります。また、財務や法務などは、海外現地の法律や税制などが関係してくるため、より専門性が求められるケースもあるでしょう。職種別採用で経理や財務などを目指す場合は、会計の専門知識にかかわる資格を取得していれば、専門知識を有していることをアピールできます。
自動車業界の現状と将来性
自動車業界の現状や将来性についてご紹介します。
自動車業界の現状
一般社団法人日本自動車工業会が公開している「日本の自動車工業2022」(※1)によれば、2021年の自動車輸出金額は14.7兆円となっており、コロナ禍の影響がある中でも、全製造業の輸出金額のうち、約2割を占めています。
また、日本貿易振興機構(ジェトロ)「主要国の自動車生産・販売動向(2023年11月)」(※2)による調査では、国別自動車生産台数において日本は第3位となっています。
日本の自動車製造における技術力は非常に高く、1997年には日本の完成車メーカーが量産型ハイブリッド車を発売しました(※3)。
今後、主流になっていく電気自動車の製造に必要な技術を日本はすべて持っていると言っても過言ではないでしょう。現在も、さまざまな企業が設備投資や研究開発に多額の投資を続けており、新たな技術の開発に取り組み続けています。
世界各国の完成車メーカーや自動車部品メーカーと戦っていく競争力は十分にあると言えるものの、自動車メーカーのグローバル競争はますます激化していくことが予想されます。今後の自動車産業の行方は、各社がどのような経営判断や事業投資をするのかが鍵になってくるでしょう。
※出典1:「日本の自動車工業2022」(一般社団法人日本自動車工業会)
※出典2:主要国の自動車生産・販売動向(PDF)│日本貿易振興機構(ジェトロ)
※出典3:自動車の開発動向と普及見通し│環境省
自動車業界の今後の展望・将来性・動向
現在の自動車業界は、「100年に1度の大変革期」とも言われており、今後の自動車の在り方や造り方、使い方を変えるとみられている「CASE(ケース)」にどう対応していくのかが注目されています。
CASEとは、「Connected」(コネクテッド)、「Autonomous」(自動運転化)、「Shared&Services」(シェアリング)、「Electric」(電動化)の頭文字を取った 用語です。2016年のパリモーターショーでメルセデス・ベンツの製造を手がけるドイツ・ダイムラー社の当時の社長、ディーター・ツェッチェ氏が「自動車を巡る新しい領域」としてCASEを提唱しました。
CASEの中でも、電気自動車にシフトする傾向は世界的な流れとなっており、環境負荷を軽減するために脱ガソリン化が進んでいます。日本が得意としてきたガソリンやディーゼルを使うエンジン車について、フランスは2040年、イギリスは2030年までに販売禁止する方針を表明しました。
日本において「国内の自動車販売台数に対する電気自動車の比率」は、2017年度の時点では1.0パーセントにも満たない状況でしたが、国が発表した「未来投資戦略2018」では、2030年時点で電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車を合わせて20~30パーセント程度に引き上げる普及目標が掲げられています。カーボンニュートラル(排出される二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを削減すること)の取り組みが進んでいく中、自動車業界にとって電気自動車の開発・普及は非常に重要な課題となっていくでしょう。
今後の自動車業界では、CASEへの対応が全体の課題になることが予想されています。コネクテッドカーや自動運転、電動化に対応するための技術や機器など、関連技術領域は広がっていき、IT業界をはじめとする異業界との技術・事業の提携がさらに増えていくとみられています。
一方、国際競争という面では、中国が頭角を現しています。中国自動車工業協会による発表では、2022年の中国の自動車輸出台数は、前年比54.4パーセント増の311万1000台で、2年連続で過去最高を更新しました。また、輸出台数のうち、電気自動車は前年比2.2倍の67万9000台となっており、全体の伸びに大きく影響しています(※)。
中国の台頭は、自動車大国である日本にとって一つの脅威となっています。今後、世界全体が電気自動車にシフトしていく中、日本は早急に電気自動車の普及率を高め、量産体制を構築し、安価な中国産の電気自動車に対抗できるだけの競争力をつけていくことが重要となるでしょう。
※出典:主要国の自動車生産・販売動向(PDF)│日本貿易振興機構(ジェトロ)
コネクテッドカー
インターネットに常時接続できる通信システムを搭載した自動車のこと。ネットワークを介した運転情報の蓄積によって自動運転車の安全性向上をはじめ、車両管理や運行管理、安全管理、ドライバーの体調管理などにも役立てることができます。例えば、運転中に急ブレーキや急加速などを行う頻度から安全運転をしているかどうか分析することで、ドライバーの保険料の金額を変動させるなどの応用も考えられています。
自動運転
自動運転技術は米国自動車技術者協会(SAE)や国土交通省によって、自動運転レベルを、レベル0~レベル5までの6段階に区分しています。2021年度より、経済産業省と国土交通省が共同で進めてきた「自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト」にて、自動運転移動サービスの実現に向けた実証実験が行われてきましたが、2023年5月、道路交通法に基づく特定自動運行として国内で初めて許可されました(※)。
これにより、レベル4の「運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)」 が可能となりました。レベル5では制限なく、すべての運転操作が自動化されるため、近い将来には、完全自動運転が実現されるでしょう。交通事故の減少や物流業界のドライバー不足解消などに役立てられることが期待されています。
※出典:国内初!自動運転車によるレベル4での運行許可を取得しました│経済産業省
MaaS
MaaS(マース:Mobility as a Service)とは、地域住民や旅行者などの個々の移動ニーズに対応し、複数の公共交通機関やタクシー、カーシェアリングなどの移動サービスを最適に組み合わせ、検索・予約・決済まで一括で行うことができるサービスのことを指します。移動の利便性を高めるだけでなく、渋滞や過疎地の交通課題、高齢者の移動手段などの問題解決に活用することも期待されています。
より高度にMaaSを実現していくためには、交通事業者の各種データに加え、自動車関連の周辺データのAI解析や自動運転技術なども重要になるため、官民双方での取り組みや連携が進められています。
世界においては、先行するフィンランドに続き、2019年11月にはフランスでもモビリティ法(別名MaaS法)が国会で可決され、本格的に推進されています。
自動車業界の志望動機の書き方と例文
志望動機の構成と、自動車業界の志望動機を書く際のポイント、例文を紹介します。
志望動機の構成
志望動機の構成は以下を参考にしましょう。
2:背景(根拠となるエピソード)
3:意気込み(入社後の活躍・貢献)
書き出しとなる結論では、自動車業界や応募企業を志望した理由を端的に伝えましょう。背景では、根拠となるエピソードを具体的に伝え、説得力を持たせることが大事です。最後に、入社後にどのような活躍・貢献がしたいか、意気込みを伝えると良いでしょう。
自動車業界の志望動機の書き方のポイント
自動車に対する興味や熱意、ものづくりに対する思いなどをしっかりと伝えることがポイントです。自動車は人命にかかわる製品でもあるため、特に、自動車メーカーには、ものづくりにおける厳しい基準をクリアすることが求められます。
現場においてもシビアさが求められますし、高い技術や知識を身につけるためにコツコツと学び続けていく忍耐力なども必要です。そのため、自動車を通じてものづくりに向き合い続けられるだけの思いを持つ人材であることが重視されます。
また、自動車産業はグローバル産業でもあるため、世界で活躍・貢献したい思い、挑戦していきたい姿勢、日本のものづくりを支えていく使命感などを伝えるのも良いでしょう。職種に関しては総合職採用を行う企業が多いので、職種を限定して理解を深めるよりも、業界全体についてどのような大変さがあり、やりがいがあるのかを理解していることが大事でしょう。
自動車業界の志望動機の例文【文理別】
志望動機の例文を文理別に紹介するので、自分らしい志望動機を書く際の参考にしてみましょう。
【文系】完成車メーカーの志望動機
多くの仲間と力を合わせ、ゼロから一つのものを作り上げ、海外と戦っていきたいと考え、貴社を志望いたしました。
私は大学で国際社会学を学び、ゼミ長として○○という論文を手がけました。ほかのゼミとも連携し、○○の取り組みについて韓国現地でフィールド調査も行いました。その際、国際化戦略において日本は後れを取っていると感じ、世界の広さを実感すると同時に、日本独自の細やかなこだわりの素晴らしさも実感し、それがちゃんと伝わっていないことを悔しく思いました。
海外の世界に飛び込んで、多くの仲間と一緒にゼロから一つのものを作っていくことに大きなモチベーションを感じたこの経験から、日本のものづくりや考え方の素晴らしさを新しい角度で世界に広めていきたいと考えました。変化を恐れず、海外で新しい挑戦を続けながらも、ものづくりの根本にある姿勢を大切にし続けている貴社で、この思いを実現していきたいと考えています。
【理系】自動車部品メーカーの志望動機
世界における自動車の安全性を高めることに技術の側面から貢献したいと考え、貴社を志望いたしました。
父が工作機械の製造に携わっていることからものづくりに興味を持ち、大学では機械工学を専攻し、チームで〇〇の研究にも取り組んでいます。貴社の△△という技術には、部品を作る工程に××を取り入れるこだわりや、チーム連携で生産体制を効率化する工夫があると知り、そこに共感しました。貴社は、自動車部品の量産技術においても精密性を追求し、より安全な自動車の製造を世界中で支えている上、自動運転技術に必要な部品なども手がけているため、強く引かれております。地方で暮らす祖父が免許を返納したことで、これからの時代には自動運転技術が重要であることも強く実感しており、日本をはじめ、世界中の自動車の安全性を高めることに携わりたいと考えました。
新たな技術に取り組み続けている貴社で、技術力を高めながら貢献していけたらと思います。
悩んだらリクナビ就職エージェントに相談することもオススメ
リクナビ就職エージェントでは、キャリアアドバイザーのサポートを無料で受けることができます。個別の面談にて、就職相談をすることができ、希望や適性に合う最適な企業の提案を受けられます。自動車業界の職種や、完成車メーカーと自動車部品メーカーの違いなどについて、より詳しく把握することに役立つでしょう。
また、応募書類の添削や面接のアドバイス、内定後の相談など、さまざまなサポートを活用することができます。自動車業界の企業選びや志望動機の作成に悩んでいる人にも役立つでしょう。
\リクナビ就職エージェントをご存じですか?/
『リクナビ就職エージェント』は就活を無料で支援するサービス。
会員登録後、アドバイザーが個別に電話相談を行い、あなたの希望や適性に合う企業選びを一緒に考えます。
エージェントだからこそできる求人情報の紹介、面接アドバイスやOpenESの添削なども行っています。
高橋若葉(たかはし・わかば)
リクナビ就職エージェントのリクルーティングアドバイザー。新卒でリクルートに入社し、主に製造業の採用支援に携わってきた。最適な学生と企業のマッチングのために、日々企業側への提案を続けている。
森山治人(もりやま・はると)
リクナビ就職エージェントのリクルーティングアドバイザー(マネージャー)。一貫して人材紹介事業に携わっており、中途エージェントではIT業界中心、その後、新卒エージェントでは自動車業界の担当を経験。現在は首都圏の会社の法人営業組織の兼任マネージャー
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。