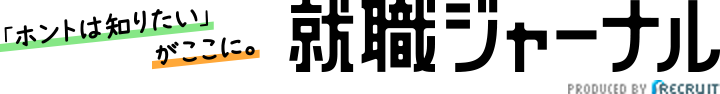はーびーやまぐち・1950年東京都生まれ。73年東京経済大学経済学部卒業後渡英。ツトム・ヤマシタ主宰の劇団「レッド・ブッダ・シアター」での役者としての活動などを経て、イギリス人写真家グループ「クオリティ・オブ・ライフ」に参加。歌手デビュー前のボーイ・ジョージとルームシェアするなど多くのミュージシャンと交流しながら、70年代の生きたロンドンを写真に記録した。帰国後、84年に渋谷パルコで初の個展「CLIMB」を開催。福山雅治、山崎まさよし、松任谷由実、ドリームズ・カム・トゥルーなど数多くのミュージシャンに信頼され、CDジャケットなどの撮影を手がける。市井の人々のいきいきとした表情を切り取った作品も高い評価を受けている。また、写真家としての活動のかたわら、エッセイ執筆、ラジオ・テレビのパーソナリティとしても活躍。2011年度日本写真協会賞作家賞受賞。大阪芸術大学客員教授、九州産業大学客員教授。
就職先が決まらず、留学する友人に伴われて何のあてもないまま渡英した
たくさんのアーティストを撮影させていただく機会がありましたが、特に福山雅治さんのファンの方々にはよく名前を覚えていただいて、僕の個展にも来てくれるんですよ。「ハービーさん」なんて声をかけてくれて、うれしいですね。福山さんを撮り始めたのは1993年の全国ツアーに同行してドキュメント写真集を作ったのがきっかけ。当時福山さんはデビュー3年目でした。このツアーの前に雑誌の取材などで数回撮らせていただいたことがあり、「背が高くて、人柄がとてもいい方だな」と感じていましたが、福山さんのことをよく知っていたわけではありません。ところが、1日、2日と一緒に時間を過ごすうちに彼の人間性に触れるわけです。
例えば、福山さんの故郷・長崎のコンサートに同行した時。リハーサル前の空き時間に「そういえば、僕の父も長崎出身なんです」と話したら、「ハービーさん、ちょっと付き合ってくれますか」とおっしゃったんです。行く先は、なんと福山さんの先祖代々のお墓。かいがいしくお墓の掃除をする彼の姿に父親思いのひとりの青年を見て、「ああ、芸能人・福山ではなく人間・福山を撮ろう」と心を突き動かされました。
写真家というのは裏方ですから、あまり名前を覚えてもらえません。著名なアーティストのCDジャケットの撮影をしたりしていても、CDを買った人は写真家の名前まではたいてい気にしないものです。ところが、福山さんは初めてお会いした時から僕のことを知っていました。彼は高校時代からパンク・ロックバンド「THE MODS(ザ・モッズ)」に憧れていて、「モッズ」のボーカルの森山さんが僕の写真を気に入っていたことから、名前を覚えていたんです。「ゆず」のふたりも初めての撮影で「今日はハービーさんが撮ってくれるんですか? うれしいです」と声をかけてくれて驚きました。彼らは布袋寅泰さんの音楽を聴いて育ち、僕が布袋さんの「GUITARHYSM(ギタリズム)」に作詞家として参加していたことから、僕の名前を覚えていてくれたんです。
僕は23歳の時(73年)にイギリスに渡り、パンク・ロックやニュー・ウェーヴ(70年代半ばに商業主義のロック音楽に反発して起きた、英国を中心とする新しい動き)全盛のロンドンでさまざまなミュージシャンと出会って音楽関係の撮影をするようになりました。ヨーロッパにレコーディングに来た日本のアーティストの撮影にも何度か声がかかり、「THE MODS」や布袋さんにもそんな中で初めて会ったんです。こういう話をすると、「ミュージシャンの撮影がしたくてロンドンに渡ったんですか?」とよく聞かれるのですが、そうではありません。大学を卒業したものの、就職先が決まらず、学生時代に同じ写真部だった友人が半年間留学するというんで、ついて行ったんです。写真が好きで、いつかはプロになりたいと思っていましたが、何のあてもないままの渡英でした。
最初はロンドンに長く滞在するつもりもなかったけれど、水が合ったんでしょうね。当時の日本では「一流大学に入って一流企業に入ることが幸せ」というようなレールが社会に敷かれているような気がしていましたが、ロンドンで出会った人はそれぞれが自分の道を自分で選択していて、それがとても楽に感じたんです。また、街で誰かを撮影させてもらうときも日本では気後れしていましたが、外国の開放感もあってか、「撮らせてください」と素直に言えました。それが心地良くて、1日でも長くロンドンにいたいと思うようになったのですが、写真を仕事にするすべを知らず、お金がどんどんなくなって…。もともとは報道写真家になろうと考えていたので、石油ショックまっただ中のクウェートに出かけて撮った写真を知り合いづてに日本の出版社に見てもらおうと動いてみたりもしたのですが、何の進展もありませんでした。
半年の観光ビザが切れそうになり、どうしようかなと考えていた時に知ったのが、当時アメリカやヨーロッパで人気のあった劇団「レッド・ブッダ」の役者のオーディションです。パーカッショニストのツトム・ヤマシタさんが主宰する劇団でした。役者に少し憧れもあったし、劇団員になればビザも延長できる。おまけに、多少は収入も得られると考えて受けたら合格。役者として100回舞台に立ちましたが、このままでは「写真家になる」という目的から外れてしまうと思って1年で退団し、貧民街にある友人のアパートに居候しながら、写真を撮り続けました。そのころにたまたま訪れたギャラリーで2人のイギリスの若者と意気投合し、彼らの家に誘われて翌日遊びに行ったら、そこは当時新進気鋭の若手写真家グループの住居兼倉庫でしてね。地下が暗室になっていて、印画紙をくれるというのでそれまで撮りためた写真100枚ほどを現像して置いて帰ったんです。それで、翌週また行ったら、「君の写真が気に入ったので、僕たちと一緒にやらないか。ここに住んでもいい」と。家賃はいらなくて、おまけに印画紙もフィルムも使い放題という願ってもない話を断るはずがありません。このグループに入れたことがプロの写真家への大きな一歩になりました。
ミュージシャンを撮り始めたのは、ツトム・ヤマシタさんが『GO』というアルバムを作っていた時にスタジオに呼んでくれたのがきっかけです。劇団員だった時はヤマシタさんとお話しすることはほとんどありませんでしたが、劇団を辞めてから応援してくれて、「撮ってくれない?」と声をかけてくれたんです。スタジオにうかがってみると、ギタリストのアル・ディ・メオラやミッチ・ミッチェル(バンド「ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス」のドラマー)といった日本でも知られる大物ミュージシャンばかり。彼らのレコーディングからコンサートまでのドキュメントを撮ったことがその後の足がかりになりました。
渡英して知り合った友人たちの中には、資金が底をつきて帰国したり、夢をかなえられずに卑屈な考えになってしまった人も少なからずいました。僕もそうなりかねない状況でしたが、何とかロンドンで居場所を見つけ、写真家としての活動を続けられたのは、たくさんの人たちに助けられたから。ラッキーだったとしか言えませんが、なぜみんなが応援してくれたかというと、僕が写真を撮ることを愛していて、実際にコツコツと撮っていたからかもしれないなと思います。

ただ人を撮りたい。被写体が有名な人であれ、市井の人であれ同じスタンスで
写真を撮り始めたのは中学2年生の時です。僕は生後2カ月で腰椎カリエスを発症。中学時代の途中までずっと石膏の硬いコルセットをつけて生活していて体育の授業も参加できず、孤独を感じていました。中学でブラスバンドに入ってようやく音楽という楽しみを見つけたのに病気のせいで退部を余儀なくされ、希望をなくしていた時に同級生に誘われて入ったのが写真部。自分にも何かを表現できるというのがうれしくて夢中になり、プロになって「人の心が優しくなるような写真を撮りたい」と強く思いました。病気のために孤独感や疎外感を味わうことが多かったので、写真で人の心が優しくなったら、自分のようなはみだし者でも生きていけるんじゃないかって。
撮りたいものがはっきりしていたせいか、うまい具合に、僕に依頼されるのは人を撮る仕事がほとんどでした。人間を撮れるんだったら何でもいいんです。被写体が有名な人であれ、市井の人であれ同じスタンスで、僕はただ人を撮りたい。どんな人でもいいところがありますから、人を撮る限り、イコールそれは僕の作品になるんです。
写真家を目指す若い人たちから「個性を出すにはどうすればいいですか」と聞かれることがありますが、個性は誰でも持っているんですよ。だって、みんな顔も違えば、育った環境も違う。僕にしても、病気を患ったことが「人の心を優しくする」というテーマを持つことにつながったんでしょうし、必ず何かあるはずなんです。問題は与えられた個性を生かせるかどうかですよね。生かすために大事なのは、好奇心を持っていろいろなことに挑戦し、「これ」と決めたことを続けることだと思います。僕であれば、写真を写すという努力をいつになってもやめてはいけない。やめると、そこで消えていくじゃないですか。
もちろんスランプに陥ったことは何度もありますよ。特にロンドンに渡ってしばらくは「これでいいのだろうか」と迷うことも多かった。そんなころに地下鉄の駅でイギリスの伝説的なパンク・バンド「クラッシュ」のジョー・ストラマーを見かけました。プライベートの時間なのでためらいもありましたが、思い切って「写真を撮らせていただいてもいいですか?」と聞いたところ、ほほ笑んで「いいよ」と。同じ車両に乗り込んで車内で撮影したところ、ジョーが電車を降りる時に僕に「撮りたいものはみんな撮れ。それがパンクだ」と言ったんです。その言葉に「自分の心に素直に撮り続けよう」と励まされました。名もない東洋人の写真家にジョーがなぜそんな言葉をかけてくれたのか、彼が生きていたら、聞いてみたいですね。
写真に出合って50年。2014年に開いた個展に来てくれたある女性が、感想ノートに「ハービーさんの写真に救われました」というメッセージを残してくれました。彼女は自殺未遂をして病院に運ばれた帰りに、偶然個展の広告を目にし、会場に来てくれたそうなんです。そして、「ハービーさんの写真を見て自殺なんてとんでもないと思った。これからは強く生きていきます」と。僕の写真が誰かの力になったなんて、うれしかったですね。写真をやっていてよかったと思いました。多少なりとも、人の役に立つこと。仕事のゴールというのはそこにあると思います。億万長者にならなくても、生きている充実感があれば人は幸せになれる。仕事でその幸せを味わえたら、それ以上のことはないのではないでしょうか。

INFORMATION
フォト・エッセイ集『雲の上はいつも青空 Scene2』(玄光社ムック/税抜き2800円)。ハービーさんの写真のテーマは常に「生きる希望」を撮ること。温かいまなざしの写真と真摯な言葉の数々が心をほんのりとさせてくれる。未発表の作品やこれまで未公開だった暗室、愛用のカメラ、レンズなども公開している。

取材・文/泉彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。