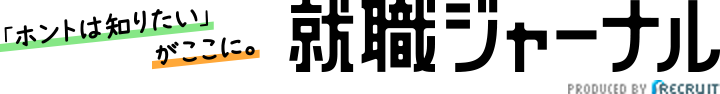にしだまさふみ・1975年東京都生まれ。学習院大学法学部法律学科卒業。在学中からお笑いコンビ「ピテカンバブー」として活動していたが、99年にコンビを解散。2000年ごろから舞台の脚本・演出を手がけ、08年『ガチ☆ボーイ』にて初めて映画脚本を手がける。以降、テレビドラマ&映画『怪物くん』『妖怪人間ベム』、アニメ『TIGER&BUNNY』など数々のヒット作の脚本、09年にはドラマ『ママさんバレーでつかまえて』で作・演出も手がけた。12年には初の小説『小野寺の弟・小野寺の姉』を出版、13年に舞台化(脚本・演出)、14年同作の映画化で映画監督としてデビュー。14年10月より放送中のドラマ『信長協奏曲』(フジテレビ月曜夜9時)の脚本も手がけている。
芸人時代から一瞬一瞬の経験を自分の財産にしようと仕事に取り組んできた
お笑い、特に落語が好きで、高校時代は落語を覚えては同級生に聞かせたりしていました。同級生といっても、中村君という友人ひとりだったんですけど…。その中村君を無理矢理誘って一時的なコンビを組み、ダメモトでホリプロのお笑い芸人オーディションに応募したら、合格。その縁で大学在学中から芸人として活動を始めました。
お笑い芸人のオーディションを受けたのは、それまでとは少し違うことをやってみたかったからです。僕は中学から大学まで学習院に通い、中学で水泳部に入ったのですが、水泳部員はたいてい高校・大学は水球部に入り、卒業後は先輩のツテで就職というのがお決まりの道だったんですね。「中学で何げなく水泳を始めたら、就職先まで決まってしまうなんて」と高校時代にふと怖くなって。それを断ち切りたい、自分で道を切り開きたいという思いがあって、取りあえず自分のやりたいことをやってみようと考えたんです。
芸人としては「ピテカンバブー」というコンビを組んで、コントのネタは自分で書いていました。一発ギャグのように理屈じゃないところで笑わせるというよりは、ストーリーの中で見せる笑いがやりたくて試行錯誤しましたが、売れなかったですね。アルバイト代を含めても年収100万円がやっとでした。
脚本を書き始めたのはホリプロの若手芸人による舞台に出演したのがきっかけです。それぞれの出演者が15分くらいの芝居の脚本を書くコンクール形式だったのですが、コントを書き続けてきた経験が生きたのか、優勝。5分のコントでは描ききれない物語や登場人物の置かれた状況も、15分の芝居ならより細かく描けることに面白さを感じました。
誰に頼まれたわけでもないけれど少しずつ長い芝居の脚本を書くようになり、お笑いコンビは解散。その後は、芸人時代の仲間たちと舞台を企画し、脚本、演出から出演までやっていました。そうやって舞台中心に活動するようになって7年くらいたったころに、映画プロデューサーの方からアマチュアプロレスを題材にした映画『ガチ☆ボーイ』(2007年)の脚本コンペに応募してみないかと声をかけていただいたんです。
コンペに応募するにあたり、最初に考えたのは、自分に何が求められているか。『ガチ☆ボーイ』の原作は舞台劇だったので、映画化にあたっては映画にしかできないことを意識して打ち出さなければと踏みました。舞台は場面設定が部室の一幕劇だったのですが、せっかくプロレスという動きのある題材なのだから、リングでの試合をクライマックスにすると面白いなと。そこで、主人公がリングで格闘する様子をプロレスの技も書き込んでリアルに表現した脚本を提出したところ、採用され、レフェリー役で出演までしました。
この作品をきっかけに映像作品の脚本の依頼も舞い込み、テレビドラマから映画化もされた『怪物くん』(10年)や『妖怪人間ベム』(11年)など原作のある作品から、アニメ『TIGER&BUNNY』(11年)といったオリジナル作の執筆まで数年の間に仕事の幅が広がっていきました。そんなときにインターネット配信のドラマ『キキコミ』(07年〜08年/監督・脚本)で僕の発想に興味を持ってくれたという編集者の方から「小説を書いてみませんか?」と依頼があり、小説『小野寺の弟・小野寺の姉』を執筆。一方で、舞台やドラマの演出の実績を買ってくださった方たちから映画を撮ってみないかというありがたいお話も頂くようになり、せっかくならオリジナル作を映画にしたいと『小野寺の弟・小野寺の姉』で映画監督デビューをしました。
芸人時代から一瞬一瞬の経験を自分の財産にしようと思って目の前の仕事に取り組んできましたが、映画を撮るにあたっては、これまでの経験すべてが生かされたと感じています。直接的に大きかったのは、『ガチ☆ボーイ』で役者として映画製作の現場を垣間見ていたこと。自分が書いた一行について役者やスタッフが一生懸命考えてくれる姿を目の当たりにしていたので、みんなが何を悩むのかがわかり、監督として何を指示するべきか迷うことがありませんでした。『小野寺の弟・小野寺の姉』では、セリフひとつをどういう間で言うのか、ひとつのカットを撮るときに構図をどうするのかといった、原作から脚本、監督まですべてに携われるからこその微細な表現をすることができ、とてもやりがいがありました。

やりたいことを実現するには、戦略を立て、一歩ずつ近づくしかない
コントでも芝居でも、自分で筋書きを書いて演出までしていたので、映画監督もいつかはやってみたいと『ガチ☆ボーイ』のころから思っていました。周囲にはあまり言っていないつもりだったのですが、映画初監督に当たり、いろいろな方から「念願かなって良かったですね」と言っていただいたので、もしかしたら、酔っぱらった時に口を滑らせたのかもしれません(笑)。
誰かに偉そうなことを言える立場ではないのですが、もし、映画を撮ってみたいという人から相談を受けたら、「まずは、いつ撮るのかを決めろ」と話します。明日すぐに撮れるというものではありませんから、戦略が必要です。映画を撮りたいなら、何年後に撮るのか。例えば「1年では難しいから5年後」と決めたなら、3年後はどうなっていなければいけないか、1年後はどうかと思い描くんです。そのために、1カ月後、明日は何をやるべきかと逆算して一日一日クリアしていく。やりたいことを実現するにはそうやって戦略を立て、一歩ずつ近づくしかないと思いますし、僕はずっとそうやってきました。
実は、『小野寺の弟・小野寺の姉』の小説を書いたのも、映画化を視野に入れてのことです。小説というのは脚本とはまた違う頭の筋肉を使うので、自分には難しいのではと思い、僭越(せんえつ)ながらお断りすることも考えたのですが、「待てよ」と。「オリジナルの脚本を映画化するのはギャンブル性が高くて資金集めが難しいけれど、原作があれば多少は保険が効いて、実現しやすくなるのでは」と考えて、思い切って書くことにしたんです。もちろん、小説を書いた段階では何も決まっておらず、映画化の保証などどこにもなかったのですが(笑)。
芸人、脚本家、役者、映画監督とさまざまな仕事をしてきましたが、僕の原点はゲームブックを自作しては同級生に見せていた小学生のころにあります。自分の頭の中に浮かんだ妄想を人に評価してもらいたいという気持ちが強いんです。だから、自分の作るものはより多くの人に見てもらいたい。老若男女楽しめるものを作りたいという思いがあります。
振り返ってみると、芸人時代はその思いだけが強くて、多くの人に見てもらうというのはどういうことかということがわかっていませんでした。コントが作品だという意識もなく、自己満足で終わっていたというか、なんとなくノリで楽しければいいというところがあり、世の中には受け入れてもらえませんでした。でも、うまくいかなかった時期に自分のダメなところを知ったからこそ、次に何をすべきかがわかりました。
妄想を作品として昇華させ、より人に響くことはないかと確かめていくのが自分の仕事。何をやるときもそれが軸になっているので、今は必要以上に悩むことがありません。今後もできることなら2作目、3作目と数年に1回でも映画を撮っていけたらとは思っていますが、ゴールは定めず、そのときどきでやりたいことに向けて進んでいけたらうれしいですね。

INFORMATION
2014年10月25日より公開の映画『小野寺の弟・小野寺の姉』は西田さんによる同名の小説をもとにした作品。引っ込み思案で恋に奥手な弟(向井理)と生命力の強い姉(片桐はいり)、彼らを取り巻く人たちによる温かくて切ない日常がコメディータッチで描かれている。「最近は脚本家として『地球を救う』という壮大なスケールのお話を手がけることが多かったので、今回は大好きで豪華なキャストで地味な家を舞台に、登場人物の一つひとつの言葉にこめた揺れる思いまで表現したいとこのテーマを選びました」と西田さん。見終えた後に、ふと家族と話したくなる作品だ。

(C)2014 『小野寺の弟・小野寺の姉』製作委員会
取材・文/泉彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。