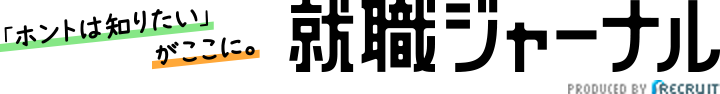さとうけんじ・1978年生まれ。武蔵野美術大学卒。フォトグラファー。世界各地の“奇妙なもの”を対象に、博物学的・美学的視点から撮影・執筆。写真集『奇界遺産』『奇界遺産2』(エクスナレッジ)は異例のベストセラーに。著書に『世界の廃墟』(飛鳥新社)、『空飛ぶ円盤が墜落した町へ』『ヒマラヤに雪男を探す』『諸星大二郎 マッドメンの世界』(河出書房新社)など。近刊は米デジタルグローブ社と共同制作した、日本初の人工衛星写真集『SATELLITE』(朝日新聞出版社)、『奇界紀行』(KADOKAWA)。2016年1月29日には、トラベルカルチャー誌『TRANSIT 佐藤健寿特別編集号〜美しき世界の不思議〜』(講談社)が刊行予定。NHKラジオ第1で『ラジオアドベンチャー奇界遺産』、テレビ朝日『タモリ倶楽部』、TBS系『クレイジージャーニー』ほかテレビ・ラジオ・雑誌への出演歴多数。
公式サイト:http://kikai.org/
ツイッター:http://twitter.com/x51/
楽しんで仕事をしていると、相手も楽しもうと思って依頼をしてくれる
台北郊外の寺院で目から手が飛び出しているご神体に出合ったり、南米のUFO村を訪れて現地の人たちの優しさに触れたり…。これまでに90カ国以上を旅して、世界中の「奇界」を追い求めて撮影をしたり、文章を書いたりしています。「奇界」というのは「人類の作り上げた奇妙な世界」という意味で、僕の造語です。
不思議で奇妙なものって、子どものころはみんな好きですよね。UFOや雪男の話に心を躍らせた記憶のある人は多いはずです。大人になるとあまり口にはしなくなりますが、科学では説明できない非合理的なものに心ひかれるところが誰しもあると思うんです。僕も同じで、特にマニアックな趣味があって「奇界遺産」を撮りはじめたわけではありません。きっかけは美術大学卒業後に留学したアメリカの大学で出された課題。大学はサンフランシスコにあったのですが、別の州の土地を撮影してきなさいというお題でした。その時に頭に浮かんだのが、子どもの時にテレビで見ていたネバダ州にあるアメリカ空軍の施設・エリア51。UFOやエイリアンの研究を行っているとうわさされた施設です。エリア51の周辺には西部開拓時代に栄えたゴーストタウンもあり、面白い絵が撮れるんじゃないかなという軽い気持ちでした。
実際にエリア51へ行ってみると、予想以上の面白さでした。施設の周囲は立ち入り禁止で、背景には何もない景色が広がっていて、近づくと監視員に制される。UFO番組で見た通りの光景でありながら、映像とは比べものにならない緊張感。一方で、エリア51の近くの街はUFO愛好家の集まる観光地と化しており、宇宙人の像がのんきに立っていたりする。以後、不思議な場所や奇妙なものの放つ独特の空気にハマり…。UFOの聖地を訪ねて南米に行ったり、雪男の謎に迫ろうとヒマラヤに出かけたりしては当時やっていた『X51.ORG』というサイトに掲載するようになりました。
UFOとか雪男というのはテレビや本でおなじみの話ではあるけれど、実際にその聖地を訪れたという人は珍しかったんでしょうね。サイトが注目されて出版社から声がかかり、初めての紀行文集『X51.ORG THE ODYSSEY』を出版。これが結構売れて、撮影や執筆の仕事が入るようになり、「奇妙な場所を訪れ続けているヤツがいる」ということでテレビに出演したりと少しずつ活動の場所が広がって今に至る感じです。
これまであまり話したことがなかったのですが、実は、美大を卒業後に1日だけ会社に勤めたことがあるんです。僕は学生時代から個人でWebや印刷物のデザインの仕事をしていたのですが、友達に「いい会社があるから、そこで働かない?」と実績のあるデザイン会社を紹介されて。デザインの仕事は楽しくやっていたので、その感じでもっと大きなことができるかなと思って面接を受け、採用されたんですね。ところが、入社初日に職場の皆さんにあいさつし、自分の席に案内されて座った途端、ものすごく憂鬱になり、「これは無理だ」と感じてその日の夕方に退職届を出しました。
その会社にイヤなところがあったのではなくて、組織というものが自分には合わないと、入社してみて初めてわかったんです。僕は特にフリーランス志向があったわけではなく、むしろ組織だからできることもあると考えていました。ただ、それまでやっていた個人の仕事では、求められた以上のものを期限内に作ることができれば、やり方は自分に任されていました。ところが、組織で仕事をするとなると、統一性を図るために使用する画像ソフトまで細かく制限されてしまう。その大切さも今はわかるのですが、「もっと効率のいいやり方があるのに」と感じてしまう自分が5年後もそこで働いている姿が想像できなかったんです。
たった1日で退職したのはほめられたことではないし、採用してくれた会社には申し訳なかったと思っています。「合わない」と思っても1年は頑張ってみるとか、せめて1週間は働いてみるというのが普通なのかもしれません。ただ、僕は学生時代からちょっとした仕事をしたり、作品を発表したりしていて、その経験を通して自分が楽しめば楽しむほど世の中に喜ばれるんだということはなんとなく感じていて。「無理」と感じたものを我慢してやっても、自分にも良くないし、相手にも迷惑がかかる。だから、辞めるなら少しでも早い方がいいと思ったんです。
幸い学生時代からいろいろやっていたので多少の収入はあって、生活に困ったことはありませんが、フリーランスには将来の保証がないので、ずっとこのままでいいのかなという思いは常に持っています。その葛藤がなかった時期はないですよ。やはり、怖いじゃないですか。病気で働けなくなったら困るなとか、退職金もないしとか(笑)、そういうことは普通に考えます。ただ、右肩上がりとはいかないまでも今のところ仕事の幅も広がっているし、何よりも自分が楽しめている。現在も10件くらいのプロジェクトが同時に動いていますが、どれも自発的にやりたいことばかりで、いまだに「仕事」という意識があまりないんです。
自分の周りで今、割とやりたいことをやってそうな人の顔を思い浮かべると、「絶対にこれになろう」と目指して今の職業をやっているという人には意外と会ったことがありません。たまたまなのかもしれませんが、好きなことをやっていたら、仕事になったという人が多い。好きでやっている人って、やはり楽しそうじゃないですか。すると「なんか、◯◯さんと一緒にやりたくて」と相手も楽しそうだからと仕事を依頼してくれて、さらに楽しい仕事が生まれる。楽しむということが仕事にいい循環を生むんじゃないかなとは思いますね。

奇妙なことの面白さをマニア以外にも気軽に楽しんでほしい
2010年に『奇界遺産』という4000円の写真集を出し、ありがたいことに好評だったのですが、企画当初は編集者から「高いと売れないから、分冊にして値段を下げましょう」と言われたんです。だけど、僕は大型本で出したいと譲りませんでした。理由はいろいろありますが、結局最後は、どういう本なら自分が欲しいかというのを基準に本を作っています。出版社には「こういう本ならこのくらいのページでこのくらいのサイズで、このくらいの値段なら売れる」という定形があるものですが、それを疑うところからいつも始めます。ただ、定形から外れたものを作るとなると、その必然性を相手に納得してもらうためのプレゼンテーションをしなければならない。非合理的なことをやるときほど合理的なアプローチが必要になります。
「奇界」を訪ねる旅にしてもそうなんですよ。旅の目的や被写体は常識とはズレていたり、合理性がなかったりするけれど、そこに至るまでの準備は緻密でむしろ合理的にやらないと、ガイドブックに載っていないような場所にたどり着くのは難しいかもしれない。…なんて言いつつ、基本的にはマイペースで遅刻することもよくあるので、偉そうなことは言えないのですが(笑)。
「奇界」を撮ったり、執筆をすることで伝えたいことは何かとよく聞かれますが、正直なところ、切実に伝えたいことは別にないんです。ただ、強いて言えば、奇妙なことの面白さをマニア以外にも気軽に楽しんでほしいという思いがあるかもしれません。子どものころから僕も割と好きなことに熱中するタイプなのですが、美大で出会った友人たちは輪をかけてマニアックな人たちが多かったんですよ。映画や本の話題ひとつでも、一般にはあまり知られていないものを知っている。それも面白いけれど、マニアというのはともすれば閉鎖的になり、「わかる人だけに伝わればいい」という姿勢になりがちなのがもったいないな、と常々思っていて。テレビに時々出演しているのも、その気持ちの延長線上にあります。
僕の写真を見てくれた人から、「世の中にはこんなヘンな世界もあると知ったら、自分の悩んでいたことがどうでもよくなった」と言われることがよくあるのですが、それはとてもうれしいですね。僕は安易に「旅は素晴らしい」とか言うつもりはまったくないです。ただ、旅の大きな効用というのは、世界にはいろいろな基準があると肌で感じられることだと思うんです。いろいろな基準や文化を見ることによって「普段、目の前にある世界だけがすべてではない」と知るだけで少し気楽になれるかもしれない。仕事選びや就職にしても同じなんじゃないかなと思います。

INFORMATION
タイの海中に石像を探し、廃墟チェルノブイリにさまよい、アフリカの呪術師と対峙(たいじ)し、南米のUFO村で人々の優しさに触れる…。「奇界」をめぐる佐藤さんの旅の全貌をつづったフォトエッセイ『奇界紀行』(KADOKAWA/定価1800円+税)。未公開作品を含む100点を超える写真を収録している。

取材・文/泉彩子 撮影/臼田尚史
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。