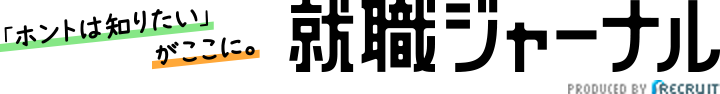ふくおかしんいち・1959年、東京都生まれ。82年、京都大学卒業。ハーバード大学医学部研究員、京都大学助教授などを経て、現在は青山学院大学総合文化政策学部教授。ロックフェラー大学客員教授。ベストセラー『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』ほか「生命とは何か」をわかりやすく解説した著書多数。画家のフェルメールの愛好家としての一面もあり、『フェルメール 光の王国』『芸術と科学のあいだ』など芸術関連の著作物や活動でも知られている。
オフィシャルブログ「福岡ハカセのささやかな言葉」:http://fukuoka-hakase.cocolog-nifty.com
プロの研究者として最も危険なことは、「絶対に正しい」という思い込み
少年時代は昆虫が大好きな「虫オタク」でした。女の子のことは私にはわかりませんが、男の子というのは、物心がつくかつかないかの段階で、好きなものの傾向がはっきりしてくると思うんですね。大きく分けて、虫や化石、星などに関心を持つナチュラル系と、電車やモデルガン、プラモデルに関心を持つメカニズム系。私は完全に前者で、理由はいまだにわかりませんが、自然が作り出したデザインの美しさをただ息を飲んで見つめていました。蝶(ちょう)の羽のはためき、カミキリ虫の優雅なひげと青く光る小さな体…。そういったものに魅入られ、きれいな蝶やカミキリ虫を集めることに夢中になりました。
蝶を集めるには、まず、どこに行けば蝶に会えるのかを知らなければなりません。図鑑片手に探してみますと、蝶は種類ごとに幼虫が餌とする葉っぱが決まっていることがわかります。例えば、アゲハはミカンやカラタチなど柑橘(かんきつ)系の葉を食べますが、アゲハと見分けのつきにくいキアゲハはパセリやニンジンの葉を食べます。葉っぱというのは幼虫にとってサラダみたいなものですから、どれを食べても栄養価は変わらないはず。それなのに、幼虫は非常に禁欲的に自分の食べる葉を限定していますし、蝶もその葉にしか産卵しない。葉を爪でひっかいて匂いや味を確かめた上で卵を産むんです。そんなふうに、昆虫採集を通して植物にも詳しくなりましたし、「豊かな自然を巡って無益な争いが起きないように、蝶は種ごとにすみ分けをしている」というような自然の摂理もおのずと感じ取りました。
一方で、自然というのは思い通りにならないということも学びました。蝶の幼虫が食べる葉を知り、探しに行ったからといって、必ずしも見つかるとは限らないんですよね。むしろ、いないことの方が多い。落胆と喜びを繰り返しつつ、「蝶は太陽光をナビゲーションとして使っているので晴れた日にしか飛ばない」「よく飛んでくる時間帯がある」…といったことをひとつずつ学び、ベストなコンディションのときに探しに行くわけです。その末に見つかるときもあれば、それでもいないときもありました。
自然というのは調べたり、行ってみたり、自ら働きかけて扉をたたかないと答えてくれないけれども、扉を叩いたからといって答えてくれるとは限らない。虫たちは私にそう教えてくれました。
のちに生物学者になってわかったのは、生物の研究においてもそれはまったく同じだということです。研究の95パーセントは落胆で終わり、思い通りにいくことはほとんどありません。むしろ、思い通りの結果が出たときは疑った方がいい。「データの取り方が間違っているから、仮説が正しく見えるだけで、実際は違う」ということは山ほどあり、仮説を疑う姿勢がないと、実験結果をゆがんで解釈しがちです。
研究者というのはプロフェッショナルであるほど自己懐疑的でありたいもの。「自分は絶対に正しい」と思い込むのは、プロとして仕事をする上で最も危険なことだと思います。

「新種」を探す喜びに胸を躍らせて、分子生物学の世界に飛び込んだ
生物学者になったのは、「虫オタク」が高じて。少年時代は新種の昆虫を発見して自分の名前の入った学名をつけることが夢でした。小学校5年生の時、図鑑に載っていない虫を見つけ、国立科学博物館に相談に行ったことがあります。昆虫博士の研究室に案内してもらい、優しく話を聞いてくれた博士が言うには「これは、ありふれたカメムシの幼生(成虫とは異なる形態の幼虫)です」。新種発見の夢はついえましたが、「昆虫の研究を仕事にしている人が世の中にはいる」と知ったのは私にとって大きな発見でした。
好きなものを研究して生活していけるなら、そんな素晴らしいことはありません。「昆虫学者になりたい」という思いから生物学を学ぼうと大学に入りましたが、入学後は昆虫の研究への関心が冷めていきました。プロの昆虫学者の多くは害虫を駆除するための農薬や殺虫剤といった産業に結び付く研究をしていて、きれいな虫、変わった虫を探すだけでは仕事として成り立たないという現実を知ったからです。
昆虫と入れ替わりにのめりこんだのが、現在研究している分子生物学。「生命とは何か」ということを分子のレベルで解明しようとする学問です。私が大学に進学した1980年代初め、分子生物学というのは米国からやってきた新しい学問であり、探究心を刺激されました。2003年のヒトゲノム計画の完成によって、ヒトの遺伝情報(ヒトゲノム)が解読され、いまや遺伝子の全体地図がデータベース化されていますが、当時の分子生物学の「細胞の森」に散らばっていた遺伝子は未知のものだらけ。昆虫採集ではかなえられなかった「新種」を探す喜びに胸を躍らせ、虫採り網を放り投げてミクロな世界に入っていったんです。
それからの私は新しい遺伝子を見つけることに没頭し、多くの生物学者と同様、遺伝子の全体地図を作ることを目指しました。ところが、研究人生が20年ほど過ぎたころ、ヒトゲノム計画によって地図は完成されてしまいました。もう探す「新種」はなく、私たちが苦労して発見したいくつかの遺伝子も、もはや大きな地図の中の点のような存在に過ぎない。私は遺伝子の研究においても、「新種発見」の夢をなくしてしまったんです。
大きな挫折を感じた出来事がもうひとつあります。私は自分が発見したGP2(グリコプロテイン2型)遺伝子の役割を世界に先駆けて突き止めようと長年研究を行ってきましたが、目に見えた成果が出ませんでした。時間と多額の資金をかけてGP2遺伝子の情報を消去したマウスを作り、どんな異常が起こるかを観察したのですが、何も起こらなかったのです。GP2が生命体の部品として何らかの役割を果たしているのは確かなのに、GP2がなくてもマウスはピンピンしている。変化がなければ何も実証されないし、論文すら書けません。どうしたものかと困惑しました。
新しい遺伝子を見つける喜びを失い、GP2遺伝子の研究も進まない。最初は落胆しました。しかし、「待てよ」と考えました。部品がひとつ欠けているにもかかわらず、問題なく動くというのは機械では考えられません。一方、生命体は何億年もの進化のプロセスで自然淘汰(とうた)が行われているので、残されている部品には何らかの役割が必ずあるはずです。その部品がなくても生命体に変化が起きないのは、何らかの方法でないものを補っているからではないか。生命は絶え間なく流れながら全体の調和を保ち、機械とは違う柔らかさを持っている。可変性を持ちながら平衡を保つ「動的平衡」にこそ生命の本質があるのではないかと気づき、執筆活動を通してそのことを広く伝えると、多くの人たちから反響がありました。
分子生物学の世界では少し前まで、生命を機械論的にとらえた研究が主流でした。私が遺伝子の全体地図の作成に研究人生をかけてきたのも、遺伝子という生命体を構成する部品をつまびらかにすることが「生命とは何か」を解き明かすことだと信じていたから。でも、ヒトゲノムで遺伝子の地図が完成されて生命についてすべてがわかったかというと、そうではなく、依然として生命は謎に満ちていました。機械論的に生命をとらえる考え方では見えないものがあるのではないだろうか。漠然とそう感じていたことが、GP2遺伝子の研究をそれまでとは別の視点からとらえ直す布石となりました。
もし、私が機械論的な視点にとらわれたままでいたら、「動的平衡」という概念にたどり着くことはなかったかもしれません。しかし、失敗に終わったと思っていたGP2遺伝子の研究結果に、私が新たな解釈を与えることができたのは、遺伝子の地図を作ることに全力を尽くし、そこに限界を感じて別の視点から考え直すというプロセスがあってこそ。既存の概念から自由になり、新しいものを発見するには、やはり道のりというものがあるんです。あるところまでいかないと見えない風景がある。どんな仕事でも、それは同じなのではないでしょうか。

INFORMATION
読書講座「福岡伸一の知恵の学校」は、福岡さんが自らの読書遍歴について語る単独講義と、さまざまな分野で日本を代表する文化人を講師に迎えたトークセッションの2部構成。講師は解剖学者・養老孟司さん、エッセイスト・阿川佐和子さん、デザイナー・佐藤卓さんなど豪華な顔ぶれ。受講者は1年間(全12回)の講義を経て、書物の魅力を公に伝えられる“ブックマイスター”を目指す。詳細はhttp://schola-sapientia.com

取材・文/泉彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。