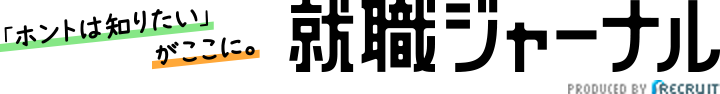たかはし・やすこ●1941年、茨城県生まれ。1964年、早稲田大学政治経済学部卒業。コピーライターとして電通に8カ月間勤務後、原宿セントラルアパートにあった広告制作会社・レマンを経てフリーランスのスタイリストに。1971年、単身ロンドンに渡り、山本寛斎さんのファッションショーを成功させる。1972年にデヴィッド・ボウイの衣装を初めて手掛ける。以後、多くのロックミュージシャンやアーティストの衣装を担当。現在も広告、CMなど第一線で活躍中。最近では北野武さん、山崎努さん、リリー・フランキーさんなどのスタイリングを担当した。著書に『表参道のヤッコさん』『わたしに拍手!』『小さな食卓』など。
前編では大手広告代理店のコピーライターを経てスタイリストになり、仕事が軌道に乗るまでをお話しいただきました。
後編ではスタイリストとして大切にしてきたことや、つらい時期をどのように乗り越えたかをうかがいます。
スタイリストの仕事は決して1人では完成しない
-スタイリストをやっていてよかったなと思う瞬間は?
そうですね。やはり、依頼してくださった方とわかり合えたり、好きなものが一緒で思わず顔を見合わせてニコッとしてしまうような時でしょうか。最初に相手が言ってくれるスタイリングのイメージがあるわけでしょう? それを具現化するのが私の役割で、「こんな感じかな」というものが相手の求めているものにぴったりハマると「わ!」って思いますね。
-20代からフリーランスとして、すべてのことを自分で判断し、責任を持つということをされてきましたよね。判断に困ったり、プレッシャーを感じたことはありますか?
あったかもしれないけれど、覚えていないです(笑)。あとね、スタイリストの仕事って私だけのセンスでは成り立たないんですよ。用意した衣装を身につけてくれる人のほかにもアートディレクターやカメラマンなどいろいろなスタッフと一緒にイメージを作り上げていく。決して1人では完成しないんです。それに、撮影のアシスタントをお願いできる仲良しのスタイリストさんや、「急ぎの衣装の制作もこの人にお願いすれば大丈夫」という職人さんなど困ったときに相談できる人が常に何人かいます。だから、あまり「すべてを自分で判断しなければ」というような気負いは持たずに来られた気がしますね。ただ、仕事をお受けしたからには責任を持ちたいので、最初から最後までどんな雑事でも全部自分でやるようにはしています。
いいことばかりじゃない。でも、ネガティブな気持ちにとらわれないように
-執筆活動もされていて、『時をかけるヤッコさん』『表参道のヤッコさん』などご著書も多いですね。
最初は周囲にいた編集者から「雑誌のコラムを書いてみて」となんだか断れない感じでお願いされたりして書いていたのですが、今は書くのが日常になっています。この間も部屋を整理していたら、書きかけの原稿が出てきて、「私、こんなのを書いていたんだ」と(笑)。コピーライターからスタイリストになった時は「もう書かなくてもいい」とホッとしたのに不思議です。スタイリストの仕事は共同作業で私には向いているけれど、これまでさまざまなことを経験してきて、そろそろ自分の内面にあるものをもっと表現したいと感じる時期になったんでしょうね。
-エッセーには、結婚、出産、介護、離婚などプライベートのことも書かれています。仕事をするのがつらい日もあったのでは?
今だから口にしますが、ありました。でも、つらい顔をしないですむように周りがしてくれたんです。50代で離婚をした時は、元気を出そうと表参道の楽器店でアコースティックギターを買ったのね。そうしたら、友人が先生になってくれて、なんとか3曲ほど弾けるようになって。仲間がよく集まるバーで披露したら、「ヤッコのライブをやろうよ」とみんなが盛り上げてくれ、友人がチラシまで作ってくれたんです。当日のお客さんは多くても20〜30人だろうと思っていたら、なんと100人を超え、2回興行になりました。気持ちが晴れて、ありがたかったですね。父の在宅介護について書いた『家族の回転扉』が第19回「読売ヒューマン・ドキュメンタリー」大賞を受賞した時は、400人が集まってお祭り騒ぎのパーティーを開きました。実はこのパーティーも、『家族の回転扉』のドラマ化が複雑な事情で頓挫し、やりきれない思いをしていた私のために友人が企画してくれたものでした。
仕事をしていてありがたいなと思うのは、人との出会い。今もたくさんの人に支えられています。ただ、いつも頼っていた人が遠い場所で生活を始めたり、お互い毎日を一生懸命過ごしたりしているうちに、いつの間にか会わなくなったというようなことも、よくあるものです。特に組織に属していないとね。仕事も同じで、今はどんなに私を信頼してくれている方でも、来月も依頼をしてくれるとは限りません。ふと気づいたら、その方の仕事をほかのスタイリストが担当していたなんてことはしょっちゅうです。
やはり心の底では寂しいですよ。若い時はドカンとショックを受けていたけれど、今はじわりとくる(笑)。でもね、そういうときに「悔しい」「悲しい」と思うのではなく、「あ、そうか」と軽く受け流して、ネガティブな気持ちにとらわれないようにしてきました。すると、いつの間にか新しい出会いもあったりする。だから、今も仕事が、そして人と会うことが楽しいです。一人の女性としては、今が一番かわいいかも(笑)。プライベートで背負うものも軽くなりましたからね。
個人の基盤というのは、はかないもの。でも、仕事も人生も、はかなさを積み重ねていくと強さになる。そんなふうに感じています。
学生へのメッセージ
私が社会に出た50年前に比べ、今は若い人が希望を抱きにくい世の中だなと感じることがあります。だから、私の話がお役に立てたかどうかは心もとないのですが、いつの時代も仕事選びで大事なのは、自分が生きていけそうな隙間を見つけることだと思います。その方法は人それぞれですが、隙間を見つけやすくするために大事なのはコツコツとした努力のような気がしています。自分で言うのは恥ずかしいのですが、私も努力家ではあったかな。学生時代からコピーライター養成講座に通ったり、仕事で用意する衣装の誰も気づかないかもしれないところに夜なべでスパンコールを縫ったり、といったことをせっせとやっていました。時々「ヤッコは運がいいね」と言われますが、運と呼ばれるものの多くは「コツコツ」の結果なのかもしれません。
高橋さんにとって仕事とは?
−その1 仕事に不安はつきもの。怖くても思い切って飛び込んでみることが大事
−その2 スタイリストの仕事は1人では成り立たない
−その3 大変なこともあるけれど、前を向いて続けていけば、地盤が固まる

INFORMATION
著書『時をかけるヤッコさん』(文藝春秋/本体1580円+税)。デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、矢沢永吉、坂本龍一、忌野清志郎から、ももクロクローバーZまで高橋さんの交友録と人生を語ったエッセー。1970年代のカルチャーの記録として楽しめるだけでなく、フリーランスとして生きる意味、離婚や介護など人生のほろ苦さも描かれており、読み応えがある。

編集後記
50年にわたってスタイリストとして活躍し、チャーミングな人柄で多くの人から「ヤッコさん」と慕われている高橋さん。数々の著名アーティストとも交友があり、取材でうかがったお話にはうらやましいエピソードがいっぱい。人からはよく「ヤッコさん、いつも元気ね」と言われるそうですが、インタビュー中、素直な気持ちを話してくれました。「毎日夕方になると寂しいのよ。そう言うと『まさか』と笑う人もいるけれど、考えてみて。息子も巣立って、私、1人よ」。でも、すかさず「毎朝電話してくれる人はいるけれどね。元気でいるか確認してくれているのね」とにっこり。「やっぱりうらやましい」と、憧れを抱かずにはいられない素敵な方でした。(編集担当I)
取材・文/泉 彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。