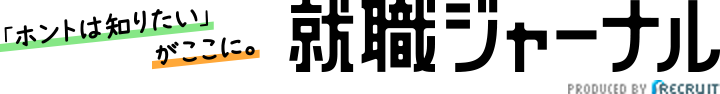マサチューセッツ工科大学メディアラボ教授 石井 裕(いしい・ひろし)
1956年生まれ。北海道大学大学院修士課程修了。1980年電電公社(現NTT)入社。88年よりNTTヒューマンインターフェース研究所で、コンピュータと人間のインターフェイスを研究。95年マサチューセッツ工科大学に招かれ、MITメディアラボ日本人初のファカルティ・メンバーとなる。2006年、国際学会のCHI(コンピュータ・ヒューマン・インターフェース)より、CHIアカデミーを受賞。19年には長年の研究と世界的な影響力を評価され、SIGCHI生涯研究賞(SIGCHI Lifetime Research Award)を授与される。※SIGCHI生涯研究賞英文サイト
全米屈指の名門校であるマサチューセッツ工科大学(MIT)のメディアラボ教授で、画期的なヒューマン・コンピュータ・インタフェース(HCI)の研究者として知られる石井裕教授。日本でも精力的に講演を行い、SNSでも常に情報を発信。そのエネルギッシュな語り口は、イノベーションを目指す多くの若者たちに刺激を与え続けています。その30年にわたる研究活動を支えたエネルギー源は何なのか、人類社会の未来を創造するためにどんなビジョンが求められているのか、石井教授の仕事の向き合い方をうかがいました。
日本がもっと元気になるために、衝突をジャンプする力に変える
──日本の企業、そこで働く人々は今、たえず技術革新や新しいビジネスを生み出そうと奮闘しています。しかしながら、GoogleやAmazonなどのグローバルなIT企業、さらには中国の新興企業に比べると、世界をリードしたかつての勢いがないようにも見えます。どうしたら日本企業はもっと元気になれるのでしょうか。
今は、より高いレベルの研究環境を求めて、学生や研究者がグローバルに移動する時代です。私が勤めるマサチューセッツ工科大学(MIT)にも、中国、インド、ベトナム、そしてヨーロッパなどから大勢の超優秀な留学生が殺到します。
ところが、世界中の研究者が研究や就業のために、どの国を目指してどのくらい移動しているかを調べると、日本はそうした人材の国際流動性が世界最低レベルです。誰も日本に来ないし、日本の研究者もどこにも出ていかない。日本では訪日観光客が3000万人を突破したと騒いでいますが、研究者の世界では人が出入りせず、水が止まってしまったような状態なのです。
【孤島】Japan isolated… ▶️ Foreign Born Scientists: Mobility Patterns for Sixteen Countrieshttp://t.co/LHgbjTJfAB pic.twitter.com/civwF4pT1N
— Hiroshi Ishii 石井裕 (@ishii_mit) May 29, 2015
──それは一体、なぜでしょう。
私は毎年アメリカから日本に戻るたびに、日本語が通じて、コンビニもあって、美味しい食べ物もあって、そもそも水が飲める。人々は礼儀ただしく、安全で安心に暮らせる。学生時代からの友人や恋人がいて、母国語で語り合いながら楽しく過ごせる─そういう日本はいいなと思います。
でも、これからの若者は日本だけに暮らし、世界を実体験することもなく、観念的に分かったつもりになっていて、はたしてそれでよいのでしょうか。違った環境に行けば、違った価値がある。大事なのは違った流派との他流試合・異種格闘技なのです。
特にグローバルに価値を認められるような研究や、企業活動をするためには、他流試合・異種格闘技が必要です。他流試合を徹底的にやらなければ、グローバルな戦いもできないし、新しい創造もできない。
一番大切な問いは、なぜ世界のトップに行けないのか、いつまでに行くのか、そのために何が足りないのか、ということなのです。

──何が足りないのでしょう?
みんな横並びの同質社会からは革新的なジャンプは生まれない。異質なものを交ぜ合わせることが大切です。ただ、それだけでは十分ではありません。異質な才能が一つの夢やビジョンを共有しなければならない。その過程で何が起こるかというと、当然、衝突が起こります。
しかし、専門を超えた新しいアイデアが生まれるチャンスもある。コンフリクト(衝突)をジャンプする力に変える力、これが決定的に重要なんです。
石井三力—「出杭力」「道程力」「造山力」とは
──そのレベルまで上がるのはなかなか大変です。
もちろん生半可なことではできません。私はその大変な道のりを表現するのに、よく「出杭力(でるくいりょく)」「道程力(どうていりょく)」「造山力(ぞうざんりょく)」という三つの言葉を使います。私の造語ですが、これをまとめて「石井三力」などと呼ばれています(笑)。
「出る杭は打たれる」という日本のことわざがありますが、若いときは打たれるのが当たり前、おまえの言うことは理解できないとか言われるけど、自分を信じて出続けられるかどうかですね。そして、それを励ましてくれる親友・同僚・先輩を見つけられるかが重要です。
そして次の段階が「道程力」。「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」という高村光太郎の詩「道程」ですよ。誰もが自分だけの新しい道を切り開かなければいけない。
そして最後が「造山力」。すでにあるものをさらに改良するのではなく、まったく新しい概念を生みだし、自分だけの山を造って、その頂上を目指し、世界初登頂する。そしてその山が世界中の誰からも見え、みんなが後から登りたくなるようにする。

──その三つの力が、今の日本に欠けているのでしょうか。
そう思います。何より、とがった杭として立ちあがろうとする前に必要な、飢餓感や屈辱感が決定的に足りない。われわれはお腹が減ることがありますね。でも、飢餓で死にそうになったことはたぶんないですよね。
しかし75年前には、そうした飢餓を現実のものとして体験した日本人が大勢いました。例えば私の父は第2次世界大戦後、当時のソ連によってシベリアの強制収容所に抑留されています。「ラーゲリ」という言葉をご存じですか。日本人の捕虜たちが収容された収容所のことです。
シベリアの凍てついた森で材木を切り出すような重労働と、一切れのパンとスープだけのような劣悪な食事で、多くの人が亡くなりました。父が生き延びることができたのは、ラーゲリの中で、目の前にあるものが食べられることが瞬時にわかったら、そして次の瞬間に食らいついたからです。絶望的な飢餓の中でも、本能的に「生きたい」という欲望が勝ったのでしょう。
もちろん、こうした飢餓状態を実体験することは、飽満な日本に住む今の私たちにはおそらく無理です。しかし想像して追体験することは可能かもしれない。文学、映画、小説、なんでもいいので、そういうのを読み込むことで、不条理や絶望感、そしてそこで生き抜く力を推察・想像・実感できるはずです。

屈辱を味わうということも大切なことです。屈辱は誇りの反対語です。自分にプライドを持っていないと屈辱感は覚えないわけですからね。私もアメリカに渡った当初は、実績もなく、最初は英語も達者ではない単なる“馬の骨”でしたから、有名な先生は誰も会ってくれない。トラックレコード(実績)がないし、ギブアンドテイクでいうと、ギブできるものがなかったからです。そこでの悔しさをいつかポジティブな意味で晴らしたいという、強い思いがありました。
こうした飢餓感や屈辱感を想像して我が身に置き換えることで、限界を突破する力が生まれてくるんじゃないかと思います。最近では、日本でも落合陽一さんなど、世界で通用する優れた研究者が登場しています。そういう人がもっとどんどん出てきて、その背中を見て、次のジェネレーションが「そうか、常識に逆らってもいいんだ」という気持ちになることが必須の条件です。
そして、やるからには「こんちくしょう」と相手に言わせなければダメです。どんな分野でもいいから、トップに立つこと。自分のオリジナルな刃で、世界と真剣勝負する。アメリカで、いや世界で、コンピュータ分野の天才とも言われるような本物の研究者たちと、本当の言葉をぶつけあって、議論できたことは、私の人生にとっても大切なことで、それがなかったら今の石井裕は存在していないんです。
人間の本質に根ざしたビジョンは未来に残り、世界を照らし続ける
──先生の講演では、「自分の人生を超えた長い時間軸でものごとを考えよ」という話がよく出てきます。自分の仕事を、2020年とかの短い射程ではなく、「2200年」くらい先の目安で考えろともおっしゃっています。しかし、私たちはつい目の前の生活、例えば卒業とか就職とか、目の前のことにとらわれてしまって、そこまでの時間軸で何かを考えることができません。
わかりますよ。ほとんどの人ができない。地球温暖化問題一つとっても、廃棄プラスチックをなくすといっても、とんでもなく大変なことで、なかなかそこまでは考えられません。会社で仕事をしていても、次の四半期の売り上げを確保したい、円満に定年退職するために勤め上げたい、と考えるのがほとんどの人です。会社を100年、200年、1000年存続させて、光り輝かせようといった、壮大なロマンを持つ経営者は、限りなく少ないでしょう。
しかし、普遍的なビジョンを考えることは、絶対欠かせないのです。私がMITに行くと決まった1995年、渡米の前にどうしても行きたかった花巻の宮沢賢治記念館で、賢治の「永訣の朝」という詩の肉筆の原稿を見たことがあります。
書いては消し、消しては書き足して、苦悩の末、原稿用紙は真っ黒になっている。それを見ていると、万年筆の先で紙を引っかく音が聞こえてくる。農作業で節くれ立った彼の指が見えてくる。そこにあったのは、宮澤賢治の身体の痕跡であり、精神の葛藤の痕跡、それがそのままが芸術になっているんです。
長い時間の中でほとんどの技術や芸術は変化し、忘れ去られていく。しかし、人間の本質に根ざした美学は、例えば宮澤賢治の肉筆原稿のように未来に残り、世界を照らし続けるはずだ、その時、私は思いました。その道を私も行かなければならないと覚悟し、コンピュータインターフェースの研究を深めてきたのです。
──先生がおっしゃる「美学」は、普遍的な価値、あるいはビジョンという言葉で言い換えることもできそうですね。
例えば、エジプトのピラミッド。ピラミッドを造った人たちは、恒星シリウスが3000年後にどこにいるかを正確にわかっていて、それを予言してトンネルを造りました。とんでもない長い未来を想像しながら、天文学の知識を建築の知識に組み込んだんですね。彼らにはビジョンがあったんです。
ピラミッドは、歴史を超えて残る普遍的な価値を生み出そうとした人類の格闘の軌跡です。最初は触れることさえかなわない、実体のない(intangible:インタンジブルな)人類のビジョンが、触れることが可能な、実体のある(tangible:タンジブルな)形で残ったのです。
未来のことは誰にもわからない。山を登ったのはいいけど、それは世界の頂上ではなく、その先に未踏峰の山があるかもしれない。だから、あると信じて登っていく。私は「未踏峰連山」という言い方をしていますけど、連山を自分で創りだす行為こそが、普遍の価値を生むのだと思います。
私も、今年、生涯研究者賞という HCI (Human-Computer Interaction) 研究者にとって最高の名誉である賞をもらったときに、「ああ、みんな、そこに山があるってついに信じてくれたんだな」という思いを強くしました。実体のなかった私の夢が実体のある形(タンジブル)になった、と。そういう体験を、ぜひこれからの若い人たちも目指してほしいのです。
人間の命は有限です。しかし、人類の未来はその先もずっと続いていく。そのことに対して、今を生きるすべての人が責任を持っている。自分さえよければいい、今さえよければいい、自分の会社さえよければいい、自分の国さえよければいい、という自己中心的な考え方からは脱しなければなりません。そして、人類の歴史の長いスパンを想像しながら、今の自分の学業や仕事と向き合うべきだ―私はそう思います。

私は、NTTからMITメディアラボに移るためのジョブ・インタビューの直後、メディアラボの創設者であるニコラス・ネグロポンテ教授の面接を受けました。
一番最初に言われたのが「君がこれまでやってきた仕事はわかった。だがここではまったく新しいことをやれ。reboot(リブート:再起動)しろ」という言葉でした。
後から聞いたのですが、それは彼のいつもの口癖らしい。それでも、その言葉に衝撃的にインスパイアされて、私はアメリカで新しい研究「タンジブル・ビット」に着手しました。
その言葉を私はいま日本の学生にもぶつけたいですね。今のぬるま湯に満足するな。そのままでいたらゆでガエルになってしまうぞ。この先、就職するのであれ、起業するのであれ、日本にいるのであれ、世界に飛び立つのであれ、新しいフェイズに飛び込んでいくということは、新しい創造へ向けて常に自分を「リブート」するということなのだ、と。
そのためには、既存の常識や慣習、既成概念といったものを疑い、まっさらな目で物事をクリティカル(批評的・批判的)に捉え直すことが欠かせません。それは私のような60代の人間にだって、まだやろうと思えば、きっとできること。ましてや、瑞々しい感性と柔軟な頭脳をもつ若者たちにそれができないはずはない。
まだ自分というものをよく知らない若者たちに、「リブートせよ」は少々厳しい言葉かもしれません。しかし、それをあえて言うのは、私がまだ日本の若者たちに多くのことを期待しているからなんです。
取材・文/広重隆樹
編集/馬場美由紀
写真/栗原克己
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。