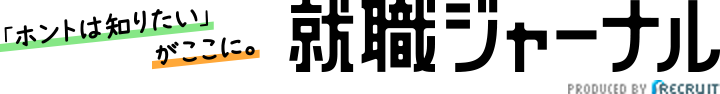才能なんてものは、自分で判断することではない
お恥ずかしい話、私は何をやるにしても最初は受け身なんです。やりたいこととか、テーマがあって鋭く切り込んでいく人の姿に憧れるんですけどね。感心するばかりで、私自身はほど遠い。最新作『正義のセ』を書くことになったのも、担当編集者とゴルフで知り合って、「連載をしませんか」と声をかけていただいたのがきっかけ。タイミングが合わなくてお断りしたのですが、何度も依頼を頂いて、ごはんまでごちそうになったので、食い逃げするわけにはいかないと(笑)。そのころ、たまたま女性検事さんと友人になって、新人女性検事を主人公にしようと思い浮かんだのですが、当時は検事が何をする仕事かも知らなかったんですよ。でも、友人の女性検事さんや担当編集チームの協力のおかげで筆が進み、3冊の本になりました。
1993年に始めた雑誌『週刊文春』の対談連載も、こんなに続くとは思いませんでした。もともと『週刊文春』ではエッセイの連載をしていたのですが、4年目くらいから調子が出なくなって悶々(もんもん)としていたところに、編集長から「エッセイはおしまいにして、対談をやらないか」とお話を頂いたんです。最初はショックでした。やっぱり私のエッセイは面白くなかったのかって。それに、対談なんて自分にできるとは到底思えませんでした。雑誌やテレビでインタビューをする機会はよくありましたが、要領よくこなせなくて、いつも怒られてばかり。インタビューには苦手意識がありました。
声をかけていただいたからにはとお受けしたものの、「できない」「向いていない」という気持ちが先に立っていたので、対談前は怖くてたまらず、悪夢にうなされたことも一度や二度ではありません。回を重ねてたまにほめられたりすると有頂天になるけれど、叱られると、「ほら、やっぱり向いてない。どうして私に対談なんてやらせるの」と心の中で逆ギレする始末でした。
それでも編集チームの方たちは見捨てずに次の仕事を依頼してくれました。その気持ちに少しでも応えたくて続けるうちに、連載開始から20年以上がたちました。いまだに対談前は緊張しますし、インタビューも得意とは思っていませんが、今さら苦手とも言えない。ありがたいことですが、「阿川にはインタビューの才能がある」と勘違いされることも多くなりました。対談を1回だけ読んでそんな評価を頂けるはずがない。続けたからこそ、認めてもらえたのかなと思います。
私はインタビューが好きではないけれど、周りが得意だと思ってくれているから続いている。歌手の布施明さんも同じことをおっしゃっていて、布施さんはデビュー当時歌手を続けるつもりはなくて、「いつか真っ当な仕事に就こう」とやめどきをうかがっていたんですって。ところが、タイミングがつかめず困っていたときに『シクラメンのかほり』を歌うことになり、「これは売れない。ようやくやめられる」とほっとしたのも束の間、この歌が大ヒット。それで、歌手を続けるしかないと覚悟を決めたそうです。
だから、まあ、仕事の向き不向きとか才能なんてものは自分で判断することではないんですよ。目の前に与えられた仕事がどんなに嫌いだろうが、向いていないと思おうが、必死でやっていれば、必ず見てくれる人はいる。それに、自分のことは意外と自分が一番よくわかっていないもの。誰かに「お前、これをやってみろ」と言われたら、その人はあなたにその力があると見込んだということなのだから、まずはやってみることが大事だと思います。
今の時代は情報があふれているから、計画をしっかり立て過ぎて就職先で思うようにならず、転職を繰り返す人もいるそうですね。でも、ここは社会人の先輩としてあえて断言させていただきます。「ここは私のいる場所じゃない」とほかへ行って、100パーセント満足することは絶対ありません。どこへ行ったって、イヤなことはあるし、イヤな奴はいます。

与えられた条件の中で、何らかの答えを見つける
小説を書くときは、どう書けば読者により面白く読んでもらえるかを意識してはいますが、基本的に自分の表現したいことを書きます。一方、インタビューの場合はなるべく自分の意思を出さないようにします。私が興味を持っていることだけを話してもらって、「ああ、うれしかった」ではお客さんは置いてきぼりになってしまう。そうならないよう、常に読者や視聴者を背後霊のように感じながらお話をうかがっています。
『週刊文春』の対談を始めたときに、編集部にお願いしたのは、現場では私もたくさん話すかもしれないけれど、文章にまとめるときはゲストの発言を優先してくださいということ。私の話は削って構いませんと言ったんです。謙虚なことを言ったつもりはなく、事実として私には造詣(ぞうけい)の深い分野があるわけではなく、家族からは「物を知らない」といつも呆れられていました。空っぽの自分がバレないように、ゲストをメインに誌面を構成してほしいと考えたのです。読んでくださったことがある方ならおわかりになるかと思いますが、自らお願いしたこととはいえ、自分の発言がまさかあそこまで削られるとは思いませんでした(笑)。でも、結果的に「ゲストの人となりがよく伝わる」と読者に支持していただけたので、良かったと思っています。
自分の発言に力がない分、読者が面白いと思うお話をゲストから引き出すのが自分の責務だという思いは強かったです。聞きにくいことをうかがわざるを得なくて、ゲストの方に不快な思いをさせてしまったり、うまく聞けなくて編集チームに叱られたことも何度もあります。でも、初めてお会いしたときは心を開いてくださらなかった方が、時を経てインタビューしてみると、「え、聞いちゃっていいの?」というお話を自分からしてくださったりもします。ただ、やはりゲストには気持ちよくお話をしていただきたいから、どうしても話したくないと相手が思っていることは「聞かない」という判断も今はします。
そのかわり、それ以上に面白いことを聞かなければいけないので、頭はフル回転。読者が面白いと思うことはワイドショー的な話題であることもあるし、ゲストの意外な側面だったりといろいろですから、ひとつのことに執着する必要はないけれど、2時間という限られた対談時間の中で何らかの答えを見つけなければいけない。そこは勝負です。
数え切れない方々にインタビューしてきましたが、何度やっても、インタビューは「おちゃのこさいさい」とはいきません。資料を読み込み、考え抜いた質問への反応がいまひとつだったり、逆に「こんな基本的なことを聞いていいのかな」という素朴な質問でこれまでにないお話がうかがえたりします。方法を決めつけないというのも大事なのかもしれないですね。
小説『正義のセ』で描いた検事の世界も、執筆にあたっていろいろと知ってみると、インタビューの仕事と重なるところがあると思いました。社会的責任の大きさや目的は違いますが、相手に心を開いてもらうことが大事という点では同じ。そして、それは人とかかわって仕事をする限り、世の中のほとんどの職業に共通していることだと思います。それにしても、相手に心を開いてもらうというのは一筋縄ではいきません。だからこそ、私の場合、インタビューでゲストがご機嫌よくお帰りになると本当にほっとします。

INFORMATION
阿川氏の最新作は、新人女性検事の成長を描いた『正義のセ』(角川書店/1巻 税込み1260円、2巻税込み1155円、3巻税込み1260円)。主人公は東京の下町にある「豆腐屋」に生まれ、小学校の時に出合った事件をきっかけに検事になった凛々子。正義感が強く、おっちょこちょいな性格が災いしてさまざまな壁にぶつかるが、家族や同期、同僚たちの助けを借りながら、正義とは何かを手探りで見つけていく。「検事を主人公にしようと考えたのは、小説のアイデアを考えていたときに偶然、ゴルフで女性検事と友達になったのがきっかけ。仲良くなるにつれて彼女のことも、検事の仕事も身近に感じ、仕事をする女性が泣いたり、笑ったりしながら一歩ずつ成長する姿を描きたいなと思ったんです」と阿川氏。これから社会に出る女性はもちろん、男性にも「仕事とは何か」を考えさせてくれる物語だ。

取材・文/泉彩子 撮影/鈴木慶子
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。