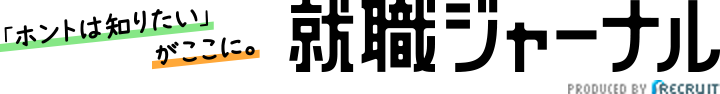とりごえしゅんたろう・1940年福岡県生まれ。京都大学文学部卒業後、65年に毎日新聞社入社。新潟支局、大阪本社社会部、東京本社社会部、外信部テヘラン特派員などを経て『サンデー毎日』編集長となる。89年、毎日新聞社退職。以後活動の場をテレビに移し、『ザ・スクープ』『スーパーモーニング』などでジャーナリスト・ニュースの職人として活躍する。2002年「桶川女子大生ストーカー殺人事件」の報道に対して「日本記者クラブ賞」、04年「警察の裏金」シリーズ特集の放送に対して「ギャラクシー大賞」を受賞。著書も多く、近著にがん闘病の経緯を描いた『がん患者』(講談社)、『祖父の流儀』(徳間書店)、『君は人生を戦い抜く覚悟ができているか』(日本実業出版)など。
大学を7年で卒業して新聞記者に。新人時代はぼんやり生きていた
「学生時代から新聞記者になるための勉強をしていたんですか?」とよく聞かれますが、そうではありません。大学では授業はそこそこに合唱団の活動に精を出し、気づけば大学7年目。ふと学生便覧をめくると、文学部の修学年限は7年と定められており、慌てました。単位取得のために奔走してなんとか卒業のめどはつきましたが、問題は就職。7年も遊んでいた学生を採用してくれる企業がそう簡単に見つかるはずがありません。本が好きだったので、出版関係の仕事に携われたらいいなと思っていましたが、出版社の採用人数はどこもごく少数。自分には無理だとはなからあきらめてしまいました。
そんな時にたまたま、同じクラスの友人が新聞社の試験を受けると知りましてね。彼の話によると、新聞社の選考は作文の比重が高く、学校の成績は関係ないとのこと。年齢制限もゆるやかで、おまけにその年は50人くらいは採用するだろうとのことでした。それを聞いて、「ひょっとしたら、自分も潜り込めるかもしれない」と毎日新聞社の記者の採用試験を受けたんです。当時の新聞社は同じ日に試験を行い、1社しか受けられませんでした。毎日新聞社を選んだのは、現場をリアルに伝えるベトナム戦争報道記事に熱のある姿勢を感じていたからです。
毎日新聞のほかにはどこも採用試験を受けておらず、後のない状況でしたから、採用が決まった時はうれしかったです。新人記者として配属されたのは新潟支局。一般的に新聞記者は入社してすぐ地方局に配属され、警察や検察を担当する「サツ(警察)回り」に始まり、地域の行政、経済、イベントなどさまざまな取材を経験します。その後、政治部、経済部、社会部、学芸部、外信部など専門の部署に配属されますが、希望の部署に行けるかどうかは地方局での活躍ぶりにかかっています。自分の書いた記事がどれだけ大きく紙面に載るかが勝負です。記者になったからには一面や社会面を飾るような事件を取材し、いずれは本社の社会部あたりに行きたいと夢を描きました。
ところが、新潟支局に赴任して数カ月で先輩から「警察は回らなくていい」と言われ、国鉄(当時)や労働、農政、教育などを担当することになりました。大きな事件を取材する仕事からは外されてしまったわけです。普通なら落ち込むところですが、僕は能天気というか、ぼーっとしていて。警察を回るのは好きではなかったので「これ幸い」とばかりに自分が関心を持ったテーマをじっくり取材しようと考えました。
そのテーマとは「米作り」。当時は政府米の逆ザヤ(売り値が買い値より安いといった、相場の価格差が本来あるべき形と逆になること)問題などから食糧管理法(1942年に制定された、食糧を政府が管理統制することを目的とした法律。95年に廃止)を存続させるのかどうかが議論されていて、日本の農業が根底から変わろうとしていました。そんな時期に日本一の米作県の新潟に配属され、農政を担当するなんてこれはまさにチャンス。「新潟にいる間に米作りについてあらゆることを勉強しよう」と時間を見つけては農家を一軒ずつ訪ねて話を聞きました。農業の現場を伝えたいという思いから、入社3年目には『この土から』という連載記事を企画。この記事には大きな反響があり、手ごたえを感じましてね。このまま農業を一生懸命取材していずれは東京本社の経済部で農政を担当し、「日本一の農業記者になってやろう」と勝手に思っていました。
入社4年目を迎えて異動の気配を感じたころから、上司にも「東京本社の経済部に行きたい」とアピールしていましたが、配属されたのは大阪本社の社会部。再び苦手な「サツ回り」です。しかも、半年ほどで大阪・岸和田市にある通信部(支局の下に置かれる出張所)に行くことになりました。事務所に泊まり込み、岸和田市や貝塚市から和歌山との県境まで大阪府南部の広い地域を記者としてひとりで担当する24時間態勢の仕事です。通信部は地域の人にとっては毎日新聞社の代表ですから、新聞配達の苦情まで対応することになります。正直なところ、最初は不本意だったのですが、次第に仕事にのめりこむようになりました。記者クラブで顔を合わせる他社の記者たちの百戦錬磨ぶりに刺激され、彼らに負けじと特ダネを求めて地域に入り込んでいくうちに、草の根からの取材が面白くなったんです。
入社7年目に岸和田から大阪本社の社会部に戻り、入社10年目にして東京本社の社会部へ異動になりました。新聞記者のキャリアとしてはここからが本番ですが、すでに30代半ば。おまけに2年ほどで週刊誌『サンデー毎日』に引き抜かれ、新聞記者になったつもりが雑誌記者に。ようやく落ち着いたかと思いきや、50歳を前にテレビの世界に転身するなんて、われながらずいぶん無軌道なキャリアですよね。でも、記者としてのイロハを学んだ新潟・大阪時代がなければ、雑誌記者として認められることはなかったですし、『サンデー毎日』時代がなければ、テレビの仕事に声をかけられることもなかった。どんな経験も糧になるというのは事実だと思います。

心の底からわき上がってくる気持ちに沿って人生を歩いていけばいい
仕事で大事なのは「直感力」だと僕は考えています。例えば、情報番組『ザ・スクープ』のキャスターを務めていた1998年に起きた「和歌山毒物カレー事件」。和歌山市園部地区で開かれた夏祭りで振る舞われたカレーに毒物が入っており、4人が死亡した事件です。当初、警察からは毒物は青酸化合物(青酸カリ、青酸ナトリウムなどの総称)と発表があり、僕も含めメディアもそのままを信じていました。でも、番組の本番で事件関連の映像を見た時に、「おかしい」と思いました。亡くなった方のおひとりが、歩いて病院に入っていく姿をとらえた映像でした。僕の取材経験から言うと、青酸カリは非常に毒性が強く、致死量が体に入ればすぐに呼吸困難を起こすはずです。すぐに番組のディレクターに話して毒物検査の方法について調べてもらったところ、警察の検査に不十分な点があることが判明。後に毒物はヒ素だとわかったのですが、『ザ・スクープ』ではいち早く「毒物は青酸カリではない」という視点で報道し、機先を制することができました。
この事件に限らず、「直感力」に助けられた仕事は数え切れないくらいあります。直感というのは最初から備わっているものではなく、経験によって得られたデータが自分の中に蓄積されてようやく働くようになるものです。そういう意味では、僕はジグザグのキャリアを歩んでいろいろなことを経験したので、幅広いジャンルのデータを蓄積できたと言えます。
ただ、それは結果論です。人生の残り時間を意識するようになった40歳前後からようやく自分が何をやればいいのかが見え、今でこそジャーナリストが自分の仕事だと思っていますが、30代までは言われたことをただひたすらやっていただけ。ずっと「何をやっているんだろうな、俺は」と思っていましたよ。大阪で「サツ回り」をしていたころなんて、情報を得ようと夜中に警察官の自宅の前でウロウロして犬に吠えられ、蚊に刺され。挙げ句の果てに何の収穫もなく、むなしい思いで星を見上げながらとぼとぼと帰る。まあ、ほとんどがそんな日々でした。
だけど、仕事ってそういうものだと思うんです。もちろん、やりたいことが早くから明確なのは素晴らしいことですが、若いころの僕のようにやりたいことがないなら、とりあえず自分が置かれた環境で、言われたことを一生懸命やるしかない。仕事のやりがいとか覚悟といったことは、そのうちに自然と出てくるものです。
これは本当に強調したいのですが、人生の目覚め方というか、いつ自分の人生に目覚めるかというのは人それぞれ違う。日本では学校を卒業したら一斉に社会に出るので、隣の人が気になりがちですが、仕事との付き合い方がみんなと同じである必要はありません。だから、本当に自分が心からそうだと思って納得して、「やっぱりこうだな」と心の底からわき上がってくる気持ちに沿って人生を歩いていけばいい。「親に言われたから」とか「みんながそうだから」と進路を決めても、そういう嘘っぽい生き方は絶対にうまくいかないですよ。やりたい仕事がなかなか見つからなかったり、うまくいかなくても、失望する必要はありません。その時々の経験を大事にしていれば、人生の春はやがて訪れます。焦らないでほしいですね。

INFORMATION
2015年でジャーナリストとして50年目を迎えた鳥越さん。著書『鳥越俊太郎 仕事の美学 君は人生を戦い抜く覚悟ができているか?』(日本実業出版社/税抜き1300円)では、長年にわたって第一線で活躍し続けている鳥越さんだからこその仕事論を現場のエピソードとともに語っている。「仕事への思いは人それぞれで、正解があるわけではありません。ただ、『僕の仕事との向き合い方はこうです』というのがひとつの例として若い方のお役に立てたらと思っています」と鳥越さん。

取材・文/泉彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。