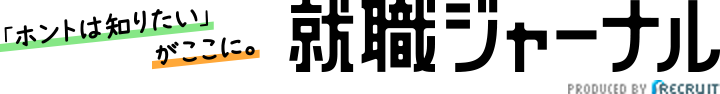たてかわしのはる・1976年大阪府生まれ。千葉県柏市育ち。米国イェール大学卒業後、三井物産に3年半勤務。初めて観た落語に衝撃を受け、2002年三井物産を退社し、立川志の輔に入門。11年、二つ目に昇進。13年NHK新人演芸大賞<落語部門>本選進出。13年度「にっかん飛切落語会」奨励賞受賞。13年、谷中・よみせ通り商店街にて林家たけ平、三遊亭萬橘と共に谷中はなし処をオープン。古典落語、新作落語のほか英語落語を演じ、ジャズ、演劇、日本酒、和菓子などジャンルを超えたコラボレーション企画にも積極的に取り組んでいる。著書に『あなたのプレゼンに「まくら」はあるか? 落語に学ぶ仕事のヒント』(星海社新書)、『自分を壊す勇気』(クロスメディア・パブリッシング)ほか。
大手商社を退職し、「薄給、プライド崩壊、自分の時間ゼロ」の落語家見習いに
落語を初めて聞いたのは25歳の時。米国の大学を卒業して三井物産に入社し、2年半がたったころです。付き合い始めたばかりの彼女と一緒に東京・巣鴨の餃子(ギョーザ)屋さんに向かう途中、あるビルの入り口に「立川志の輔独演会」というのぼりが立っているのが目に入りました。僕は落語にはまったく興味がなかったのですが、彼女が「有名な人だよ。当日券があるか聞いてみようよ」と言い出しまして。受付で尋ねたら、「2枚なら大丈夫ですよ」ということで、「餃子はお預けか」と心の中で残念に思いながら席についたんです。
私はテレビやラジオでも落語を聞いたことがなく、漠然と「おじいちゃん、おばあちゃんの娯楽」だと思っていました。ところが、志の輔師匠が高座(こうざ。芸を演じる場所)に上がると「何だこれは」と衝撃が走りました。マクラ(落語の本題に入る前の話)から面白くて面白くて。新作落語が始まると、呼吸困難になるほど声を上げて笑いました。斜に構えた性格だった私があんなに笑ったのは人生で初めてだったと思います。次に「井戸の茶碗(ちゃわん)」という古典落語が始まったのですが、40分ほどの時間をまったく感じないほど噺(はなし)の世界に引き込まれました。何よりも驚いたのは、聞いているうちに頭の中に情景が浮かび、登場人物が動き出して、師匠の姿が目に入らなくなったことです。以前から演劇やコメディーは見に行っていて、ライブの面白さは知っていたつもりでしたが、落語は私がそれまで見てきたものとはまったく違いました。
衝動的に「落語家になりたい」「志の輔師匠のようになりたい」と思いましたが、落語のことは何も知りません。まずは片っ端から落語を聞いてみようと毎日のように都内の落語会や寄席に通いました。半年たっても気持ちが変わらなければ、落語家になろうと思ったんです。それからは、商社の社員にとって大事な取引先との飲み会や休日のゴルフも断って、落語、落語でした。落語について知れば知るほど「やはり志の輔師匠のもとで落語をやりたい」という思いが膨らみ、会社を辞めて志の輔師匠に入門しました。
落語の世界に入るにあたって、試験というものはありません。会社なら入社試験がありますし、スポーツ選手なら実績や入団テスト、歌手や俳優ならオーディションといった試験があって、最低限の技術や知識が求められます。ところが、落語の場合、熱意があると師匠に見込まれさえすれば、入門して「見習い」になることができます。ただし、「見習い」は師匠の身の回りのお世話が仕事で、無給。「弟子」と名乗ることも許されません。師匠に自分の弟子としてふさわしいと認められ、芸名をもらって「前座」という身分になると、初めて高座に上がらせてもらえますが、それでも半人前以下の扱い。すべての行動について師匠の許しを得ることが必要で、師匠の付き人としての仕事もやらなければなりません。収入も最初は月収1万円がせいぜいといったところで、アルバイトもできませんでしたから、会社員時代の貯金を切り崩してやりくりしていました。
落語家として自由に活動できるようになるのは、「前座」の次の「二つ目」から。それまでは師匠の身の回りのお世話を通して、落語への熱意を試され続けます。では、どうすれば、熱意を認められるのか。それは、修業時代に周囲から言われ続けた「師匠を快適にしろ」というひと言に尽きます。ぎょっとする言葉ですが、「師匠ひとりを快適にできなくて、お客さんを快適にできるか」という意図なんですね。今ではうなずけますが、ひとりの人を徹底的に快適にするということがどういうことなのか、当時の私にはまったくわかりませんでした。
私は小学校時代の数年と大学時代を米国で暮らし、いかにして自分を他者にアピールするかが問われる環境で教育を受けました。日本流の気づかいというものが身についておらず、落語界に入る時も母から「あんたの中に落語に必要なサービス精神なんてこれっぽっちもない。1ミクロンもない」と猛反対されたほどです。そんな人間がいきなり「お前は何者でもない。とにかく師匠を快適にしろ」と言われたわけですから、頭では理解できても、体がついていきません。おまけに私は器用なタイプではありませんから、言われたことをすぐにはできず、師匠から「お前に落語は無理だ」と何度お叱りを受けたかわかりません。
一般的に前座になるまでには長くても半年、その後3、4年で二つ目に昇進という人も少なくありません。ところが、私は前座になるまでに1年3カ月かかり、二つ目まではさらに7年かかりました。「薄給、プライド崩壊、自分の時間ゼロ」の修業生活を8年3カ月続けたことになります。その間に落ち込んだことは数知れず…。でも、やめようと思ったことはありません。
やめなかった理由で一番大きいのは、これが自分のやりたいことなんだという確信があったからです。才能があるのか、稼ぎがあるのかないのか、そんなことは関係ない。ただ、自分のやっていることに迷いがなかった。そういう意味では、商社時代の方が葛藤がありましたね。海外の大学に在学している学生向けの採用枠でたまたま入って、やりたいことが明確ではありませんでした。鉄鉱石部という営業部署にいて、会社は楽しかったんです。だけど、「あのビルもあの橋も、俺たちが輸入した鉄鉱石でできているんだ」と目を輝かせて語る先輩たちのような思いを鉄に対して持つことはできなかった。落語に出合ってからはそんな心のモヤモヤがなくなりましたから、何があってもつらくはありませんでした。

修業の時期に大事なのは、直球で思いっ切り勝負すること
個人主義で合理的な考え方になじんでいた私にとって、落語の徒弟制度というのはまさにカルチャーショック。当初は理解できないこともたくさんありました。でも、二つ目になり、すべての責任を自分で負う厳しさを知った今、徒弟制度には若い人たちを守ってくれる側面もあると感じています。例えば、寄席や落語会では「前座までは料金外です」という言葉をよく聞きます。その言葉の是非はともかく、修業中は一人前扱いされないかわりに、結果や責任も問われないということ。捉え方によっては、結果を気にせず勝負できる恵まれた期間です。
修業の時期に大事なのは、直球で思いっ切り勝負すること。落語においてプロの条件は、相手の反応を的確に把握することだと私は考えていますが、肩書が上になるほどその把握には高い能力が求められるようになります。肩書から読み取れる「面白い」というイメージだけでお客さんが愛想笑いをする場合があり、自分が本当に面白いのか判断がつきにくくなるからです。その点、前座に対するお客さんの反応はストレートですから、何が受けて、何が受けなかったのかをそのまま受け止めて次に生かすことで成長につながります。ところが、この時期に大きくスベることを怖がって同じようなネタを繰り返したり、その場だけで受ける内輪ネタに走ったりすると、正しいデータが蓄積されないように思います。まあ、私の場合は不器用だったので、スベってばかり。失敗を気にしていられないだけだったのですが…。
ただ、今は私の修業時代と比べて落語界もビジネスの世界も「即戦力」が求められるようになっていますから、難しいところはありますよね。「修業時代に地肩を鍛えておけば、いつか役立つ」と周囲から言われても、なかなか信じられず、早く結果を出そうと焦りがちです。でも、年齢や経験を重ねると、失敗がもっと怖くなります。少しでも若いうちに変化球を使わず、思いっ切り勝負した方がいいと私は思います。
もうひとつ修業を経験して大きかったのは、客観性を養えたことです。「自分はこういう人間なんだ」「自分はこういうことをやってきた」という過去を一時的に捨て、「師匠を快適にするために、今、自分はどうすべきか」だけを自らに問い続けた修業時代。可能な限り師匠と同じように考えるということを習慣づけたことで、自分以外のもうひとつの価値観を身につけることができたのです。
そんなことをしたら、自分がなくなってしまうと思うかもしれませんが、自分というのはそう簡単になくなりません。むしろどうしても捨てられない「自分」が色濃く残ります。そこに客観性がもたらされることで、自分のやりたいことをお客さんにわかりやすく伝えることができる。ビジネスの世界でもこれは同じで、「自分の仕事によってひとりの人を快適にするにはどうすべきか」を徹底的に追求することは大事なのではないでしょうか。
落語の世界に入って13年。二つ目になったころまでは自分の経歴を邪魔だと思っていました。「米国の大学を卒業して三井物産から落語家に転身」と知られれば、周囲は経歴に意識が向いて、落語そのものを聞いてくれなくなってしまう。だから、お客さんには経歴をひた隠しにしていましたし、英語落語の誘いを受けても消極的でした。英語落語をやると、本来の落語から逃げていると言われるのではと思っていたからです。
その私が英語落語もやるようになったのは、二つ目に昇進した翌年に参加したシンガポール国際ストーリーテリングフェスティバルがきっかけです。参加者のほとんどはアマチュアでしたが、純粋に自分たちの物語を大事にしていて、愛情をこめて語っていることが伝わってきました。その姿を見た時に、私自身の落語への姿勢を問い直したんですね。プロとしてやっていくうちに周囲の評価や批判を気にしすぎるようになって、「こんなに面白い噺があるから、誰かに伝えたい」という気持ちが薄れていたなと。実際、英語落語をやってみると外国人にも大きな反応があり、言語なんて細かいことにとらわれず、もっと噺そのものの力を信じてやっていこうと決めたんです。
今は古典落語を中心に、新作落語、英語落語の三本柱でやっていますが、根本は初めて師匠の落語を聞いた時に衝撃を受けたような「消える芸」をやりたいんです。自分の存在を感じさせないくらいお客さんを噺の世界に引き込めるようになりたい。生涯をかけてそんな仕事ができたらと思っています。

INFORMATION
日比谷コンベンションホール大ホール(日比谷図書文化館 地下1階)にて、立川志の春さんの独演会「Tuesday Night Live in Hibiya〜火曜落語劇場〜」が毎月行われている。次回は2015年9月15日(火)に開催予定だ。詳細は立川志の春公式サイト(http://shinoharu.com)。

取材・文/泉彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。