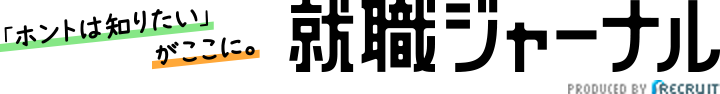前言撤回もしていい。やってみなければ、わからないこともある
「誰でも名前を知っている賞は反響が違う」と今回受賞してあらためて実感しました。15年間作家として仕事をしてきて、いくつかの文学賞も頂きましたが、芥川賞は候補になっただけでも周りの人たちの期待がとても大きいですね。編集者など一緒に仕事をしてきた人たちだけでなく、実家の近所のおばさんとかも「頑張ってや!」と声をかけてくれたりして…。受賞で皆さんに喜んでもらえたことがうれしかったですし、これからもより面白いものを書かなければと気持ちを新たにしました。
「これで憧れの印税生活だね」と言われたりしますが、世間一般のイメージと実際は違いますし、受賞後の生活は以前と変わらず、真っ白な原稿を前にうなる日々。この仕事をして長いですし、今まで通り仕事を続けていくだけです。思い起こせば、私自身は「印税生活」というものに憧れたことがありません。小説を読んでもらいたいから書いてきたので、生活に華やかさを求めたことはなかったんです。
母が美容師をしている影響で、仕事というのはずっとしていくものだと自然に思っていました。ずっとやるなら、好きなことの方がいいだろう、と。本や漫画やテレビなどが好きで、とにかく作る側になりたかったのですが、言葉や文章のことが向いていそうだったので中学生のころには小説家になろうと考えていました。ほかにやりたいことが思い当たらなかったので、私にとってはすごく現実的な職業選択でした。
小学生のころからいつもストーリーを考えて文章を書いていましたが、私は根気がなくて断片ばかり(笑)。初めて小説を最後まで書き上げたのは高校2年生の時です。同世代の男の子を主人公にした話で、原稿用紙50枚くらい。友達は面白いと言ってくれましたが、まだ作家になるレベルではないと思って応募はしませんでした。
その後も書き続けてはいましたが、応募をしなければ小説家にはなれないと遅まきながら気づいたのは、就職が現実的になってきた時期です。小説家になることしか考えたことがなかったのに、大学3年になっても小説家になれるめどはまったく立っていなくて。付け焼き刃で始めた就職活動もうまくいかずアルバイト生活を覚悟していたら、卒業間近になって学部の先輩のご縁で運良く産業機械メーカーの事務職に決まりました。このままでは小説家への道から外れてしまうと焦り、30歳までに作家一本で生活しようと具体的にスケジュールを立て、まずは文芸誌に応募しなければと行動に移したら、会社員1年目に書いた作品が最終選考に残り、3年目から仕事として書くようになりました。
私が小説家になれたのは、小説や映画が心のよりどころだったこともありますが、思い込みと勘違いに支えられたところも大きかったと思います。何しろ、小説家に「なれたらいいな」ではなく「なる予定」と決め込んでいましたから。小説を書いたこともないのに雑誌で小説家のインタビュー記事を見て「私もこうやって取材されるんだろうな」なんて想像していた小学生の自分を思い返すと笑ってしまいますが、強いイメージを持っていてよかったのかもしれません。
今、小説を書き続けていられるのも、この思い込みが幸いしています。原稿が書けず苦しいときも、自分にはほかに逃げ道がないので、いくら悩もうが書くしかない。この苦しさを超えるためには書くしかないんですよね。
ただ、この思い込みも、頭の中で「小説家になる」と決めただけでは厄介(やっかい)なものに過ぎなかったと思います。実は、高校時代に小説を書き上げられたのは、「手に職をつけなさい」と高校進学のときに母から出された条件で、美容専門学校の通信課程を受講しスクーリング(通信教育における面接授業)に参加したのがきっかけでした。クラスには、働きながら美容師資格を目指す勉強熱心な人ばかり。中途半端な気持ちでそこにいる自分が申し訳なくて、自分は自分のやるべきことをやろうと小説を書いたんです。また、すでにお話ししたように、小説家になるために具体的な行動を起こそうと思ったのも、企業への就職という私にとっては予想外の状況に身を置いてみたからこそです。
自分のやりたいことというのは、誰もが最初からはっきりしていてまっすぐ進んでいけるわけではありません。私自身がそうだったように、やりたいことはあるけれど、具体的な道筋がわからないという人も多いでしょう。それでも、とにかく動いてみると、見えてくるものがあります。その時のポイントは、なんでも真剣にやってみて、「違う」と思ったらやめること。一度始めたことはなかなかやめづらいものですが、やってみなければわからないこともあります。前言撤回をしてもいい。あやふやな状況のままでいるよりは、行動してみた方がいいと思います。

仕事との距離感は人それぞれ。「夢」という名の呪縛にとらわれないで
一度就職したからには3年は勤めようと思っていたので、4年を前に産業機械メーカーの事務職を辞めました。器用に気持ちの切り替えができるタイプではないので、二足のわらじの生活で会社に迷惑をかけてはいけないと考えて退職を決めましたが、会社員生活をしながら書くことは苦ではありませんでした。事務職は意外と私に向いていたし、同僚と話すのも楽しかった。退職後しばらくは人恋しくて、「会社に行きたい」とときどき思ったりしたものです。
会社に入ってわかったのが、仕事と生活のバランスは人それぞれということ。私自身は好きなことを仕事にするのが一番いいと思っていたけれど、休暇を利用してモンゴルで開催されるバイクレースに出たり、会社帰りに習い事をしたり、会社の仕事をしつつ趣味ややりたいことを楽しんでいる人もたくさんいて、それもいい生活だなと感じました。学生時代はそれこそ就職イコール「自分の好きなことはできなくなる」というイメージを持っていたけれど、そうじゃないんだなと。好きなこと、やりたいことを仕事にしてそこでまい進する人もいれば、ある程度分ける生き方もあって、人によって仕事や就職の位置づけは違うものなんですよね。学生からそのまま小説家になっていたら、視野が狭かったし、そういうこともあまり実感できていなかったかもしれません。
子どものころからやたら「将来の夢は?」「やりたいことは?」と聞かれることもあって、夢がないと悩んだり、やりたいこと以外の仕事に就くのはよくないイメージを思っている人も多いんじゃないでしょうか。でも、「夢」や「やりたいこと」という名の呪縛にとらわれないようにしてほしいと思います。仕事は「お金を稼ぐ手段」という人もいれば、仕事で自己実現したいという人、仕事も趣味もそこそこでという人もいて、どちらがいいとか悪いとかいうことはありません。大事なのは、自分にとってちょうどいい仕事との距離感を見つけること。学生のあいだに知っている職業なんて限られているし、実際に仕事をしてみなければわからないところはありますから、あまりかたくなには考えない方がいいかもしれませんね。
私自身は小説家になることを「夢」と思ったことはありません。子どものころから母の美容室で手伝いをして仕事というのがどういうものなのかおぼろげに感じてもいたので、小説家になっても急に華々しいことは起きなくて、苦労しながら続けていくものなんだろうなと考えていました。
それでも小説家になりたかったのは、小説や文章が好きだということと同じくらい、「わからないことは知りたいし、知って面白かったことは、隣の人にも教えたい」という好奇心と言いたがりみたいなところゆえだと思います。私にとって小説は、それまで気づかなかったものの見方を与えてくれ、現実の世界を少し面白くしてくれるもの。新しいものの見方を知ると、日常の何気ないことがいきなり楽しくなることってありますよね。例えば、少し前にエスカレーターマニアの人のWebサイトを見つけたのですが、それからは、ただの地下鉄の乗り換えもエスカレーターに目が行って退屈しません。そうやって新しい視点をくれるものというのは小説のほかにもたくさんありますが、小説だからこそできることもある。これからも、そこを突き詰めていけたらと思います。

INFORMATION
芥川賞を受賞した『春の庭』(文藝春秋/税抜1300円)の舞台は、東京・世田谷区にある、取り壊し寸前のアパート。そこへ引っ越してきた主人公・太郎は面倒なことが嫌いな性格だが、隣の一軒家をのぞくことに異様な執着を見せる隣人女性・西にいつの間にか巻き込まれ——。街や建物、風景の描写がみずみずしく、日常に満ちているちょっとした楽しみに気づかせてくれる作品。

取材・文/泉彩子 撮影/刑部友康
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。